その青少年時代
1 生誕から書店見習い時代まで
父親クリストフ・ゴットリープ・ニコライ
わが主人公クリストフ・フリードリヒ・ニコライは、1733年3月18日、プロイセン王国の王都ベルリンで、書籍商クリストフ・ゴットリープ・ニコライの息子として生まれた。4人の男兄弟の末の男子であったが、このほか4人の姉妹も含めて何人かは、早死にしていた。ベルリンからあまり遠くないヴィッテンベルク市の市長を務めていた彼の祖父も、本業は書籍商であった。
この祖父の店で働いていたのが父親であったが、祖父の娘と結婚したとき、そのベルリンの支店を結婚持参金として与えられたのであった。この書店には国王から特権が付与されていたが、書店を受け継いだ父親は、やがてその書店にいくらかの名声を付け加えていった。当時プロイセン王国を統治していたのは軍人王と呼ばれているフリードリヒ・ヴィルヘルム一世であった。そしてその後継者となったフリードリヒ大王は、皇太子時代にこのニコライ書店をしばしば訪れていたことを、のちにわが主人公フリードリヒ・ニコライと会見したときに明らかにしている。
当時ドイツの書籍商は一般に書店経営と出版業を兼ねていたが、父親のゴットリープ・ニコライは、出版業の面で、時代の文学的要請に対して確かな勘と才覚を有していた、といわれる。つまり当時大きな発行部数を見込め、儲けも大きかったドイツ語・ドイツ文学関係の書物に目をつけていたのだ。これらと「当時評判の良かった学校の教科書は、彼の名声を高めるのと同時に、その経営基盤を改善した」わけである。
この父親の性格は、倹約、勤勉、厳格そして道徳心や宗教心の厚さ、といった言葉で表現できるものであった。そしてそれらはまたプロイセン王国に生きていた中流市民のプロテスタント的な生活信条そのものであった、といえよう。これはまたプロイセン王国を軍事官僚国家に仕立て上げた軍人王の統治方式に倣ったものともいわれる。
忠実な臣下であったニコライの父親は、時代とその身分に見合った形で、その家族と奉公人と商売を取り仕切っていた「家父長」だったのだ。
ニコライの幼少期
この父親の性格のいくつかを、いくぶん薄めた形で息子のニコライも受け継いでいる。ただ宗教に対しては息子はやがて父親とは大きく異なる立場をとるようになった。またニコライは原ベルリンっ子の典型として、仕事熱心さ、批判精神そして現実感覚の三つを併せ持っていた。これらの三つの要素がやがて彼の運命を大きく左右するのであるが、この点については徐々に明らかになっていくであろう。
権威主義的な父親の厳しさを和らげてくれたのが、母親であったが、この母親をニコライは5歳の時に失うなど、その幼少時代から彼は家庭の温かさには恵まれなかった。この家庭的な保護の欠如が、やがて彼の生涯に大きくかかわっていくのである。そしてその精神生活にも影響を与えたのであった。
中等教育期
幼少期を過ぎて、やがてニコライは教育熱心な父親によって、三つの中等教育機関に通うことになった。まず1746年、13歳でベルリンのヨアヒムスタール・ギムナジウムに1年間通ったのち、ハレにあった孤児院の学校に移り、さらに1748年にはベルリンの実科学校へと転校した。最初に通ったギムナジウムでは、上級生による新入生いじめが、やりたい放題に行われていた。新しく入ってきた生徒は、上級生から好き勝手に殴られたり、いじめられたりしていたが、それに対して教師はなすすべがなかった、という状況にあった。
この学校での息子の発展が望めないことが分かり、父親はハレにあったフランケ財団経営の孤児院の学校に息子を移した。この学校はもともと敬虔主義者のA・H・フランケによって17世紀末から、キリスト教の敬虔な精神の育成と有用な知識の獲得をその教育の最終目標に掲げて作られた一連の学校の一つであった。
しかしニコライがこの学校に移されたときには、フランケの創設から半世紀が過ぎていて、敬虔主義のうわべとかたくなな形式主義に支配されていた。これはニコライの父親の見込み違いであったのだ。敬虔主義を嫌っていたフリードリヒ大王に言わせれば、ただ「偽善的な坊主ども」と「プロテスタントのイエズス会士」を作っていたことになる。ニコライ自身は、のちにこの学校について次のように振り返っている。
「教育のやり方もまたその中身も、すべて伸びようとしている若者の精神の力を抑圧することに向けられていたようだ。魂の抜けた無為無策とうわべを取りつくろった態度が、信心深さなのであった。監督官や教師の下での奴隷的な服従と、信心深さだけが称賛されていたのだ」
ただニコライもシュタインというギリシア語の教師については良い印象を持っていて、彼がいたおかげでギリシア語を勉強したのだと、述べている。このシュタイン先生からニコライは、ギリシア語で書かれた新約聖書の一部を習い、さらにホメロスの『イリアス』から数節を教わったとき、ハレ大学で哲学を勉強していた兄のザムエルにこのホメロスがいったいどんな人物なのか、問い合わせている。それに対して「彼は私にホメロスが文学の頂点に立つ人物であることを教えてくれたが、当時15歳の少年だった私にとっては、ホメロスはまだ早すぎたようだ」と書いている。
とはいえホメロスの存在はその後もニコライの心に残り、のちに出版業を受け継いでから発行した、初期のたいていの出版物には、出版社の標章としてホメロスの肖像が印刷されていたのである。
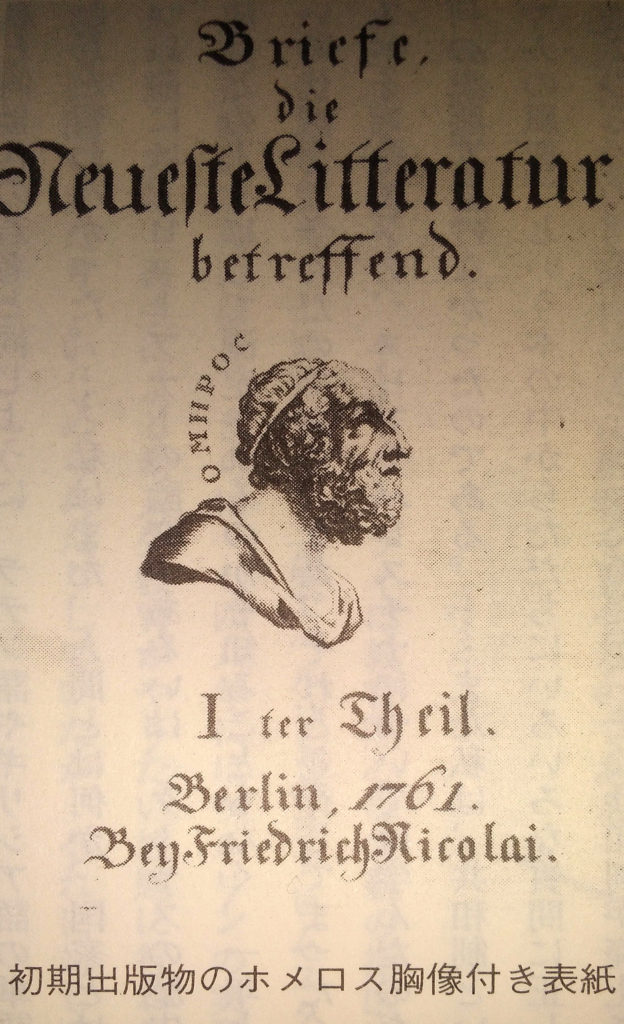
初期出版物のホメロス胸像つき表紙
しかしシュタイン先生に代わって、細かなことにうるさい教師になってからは、この学校はニコライにとってますます息苦しいものになったようだ。
文学への開眼
学校の中の、こうした息苦しさから、ニコライは、もっと自由で開かれた世界にあこがれ、世俗的な文学を読みたいという欲求にかられるようになった。そんな時、兄のザムエルからニコライのもとに、一冊の文芸雑誌が送られてきた。この雑誌は『ブレーメン寄与』という名前であったが、そこには新しい啓蒙主義文学が紹介されていた。この雑誌を通じてニコライは初めてドイツ詩の概念を得たというが、それはまさに彼の「文学への開眼」であったのだ。
しかしニコライはこの雑誌を学校で自由に読めたわけではなかった。そのことについて彼は次のように書いている。
「敬虔主義に凝り固まったこの学校では、・・・世俗的な本、とりわけドイツ語の本は読むのを禁じられていた。それでも私は何人かの友達に、私の宝物ともいえる『ブレーメン寄与』を持っていることを打ち明けた。ところがそのことがやがて露見してしまった。当時は監督官に対しては、頭を垂れて密告するのが一番だと勧められていたのだ。そのため互いに信頼できる生徒は少なかった。もっとも信心深そうに見せかけていた者が、一番信頼できなかったのだ。私は自分の宝を、人の目につかないところ、つまりわら布団の中に隠したが、それでも見つかって、没収されてしまったのだ」
実科学校への転校
こうした状況を知った父親は息子を再び、ベルリンに新設されて間もない実科学校に転校させた。まさに中国の故事にみえる「孟母三遷の教え」を、地で行くものであったといえよう。
この学校はJ・J・ヘッカ-によって、1747年5月に設立されたものであった。「ヘッカーはハレの教育施設で教師としてフランケ流の教授法を徹底的に学び、1738年から説教者としてベルリンに招聘され、そこでも引き続き研究を行った人物である。・・・1747年ヘッカーはコッホ通りに、図工、幾何、技術、建築、手工芸、家政などを教える最初の小さな実科学校を開設し、翌年にはその学校の教師の数はすでに20名を数えるようになっていた」
この学校は「本来、職人養成学校として設立された学校であったが、しまいには神学、ラテン語、ギリシア語、ヘブライ語、地理、歴史、正書法、実業書簡の書き方、数学、算術、音楽、植物学、解剖学、商学、鉱山学などが教えられるようになった。こんな状況だったので、口の悪い人からは、子供たちにこれだけのものを学ばせ、専門家の先生より利口にさせて、どうしようとするのだ、と非難された」
それはともかく、ニコライはこの実科学校に入学したのであったが、ここでの1年間に彼は、その前の二つの学校で得たものよりも、はるかに多くのものを得たという。その具体的な様子を、少し長くなるが、ニコライの自伝から引用することにする。
「私は実科学校に入学したが、そこは全く新しい世界であった。前に通った学校での授業が、わたしには全く面白くなく、無意味であったのに、この学校で学ぶことはすべて興味深く、変化に富んでいるように思われた。そのため最初の一か月、私は喜びのあまり我を忘れた。
植物学の授業では、春から秋にかけて、遠足が行われた。いろいろな雑草、花、木の葉を、家に持ち帰り、乾燥させ標本として、各自が保存することによって、植物の名前を覚えた。
解剖学は、骨格の模型と銅版画によって学んだ。冬になると数回、大学の解剖学教室に連れていかれ、死体を通じて内臓の位置や脳の構造などについて学んだ。
農業経済は、かつて実際に農場を経営していた人から教わった。この先生は私たちを外に連れ出して、農作業の実態を見せてくれた。
理化学では、まず一般的な知識が教えられ、また実験も行われた。理科学教室には、空気ポンプや気圧計、温度計、その他の物理の実験機材が置いてあった。さらに電気は当時まだ全く新しいものであったが、私たちは電気で動く機械のある場所に連れていかれ、当時としては最高級の実験を見せてもらった。
つぎに銅版画や石膏像を見ながら、人間の身体を描いた。最終段階では、一か月かかって、実物のモデルを使って人体をスケッチした。またあらゆる種類の建築学の製図の描き方を教わった。そしてかなり大きな実科学校の校舎を実測させられたし、建物の全体と個々の部分の平面図と立面図を素描し、仕上げをさせられた。
天文学は、ツィンマーマンの天体儀によって教えられた。冬の澄み切った大空にちりばめられた星がくっきり見える夜、戸外に出て星座を観察した。また何度か大学の天文台に連れていかれ、天文学の計測機器や天体観測に関する知識を習得した。
最高に面白かったのは、製作実習の時間だった。この時間には国王の法令に従って、当時ベルリンで親方になろうとする職人全ての資格審査合格作品が、生徒たちのために提示されねばならないことになっていた。クラスの全員が週に2回、ベルリンにあるマニュファクチャーや工場の見学に連れていかれた。そして各人が自分の目で見たものを記録しなければならなかったが、これは同時にわかりやすく明瞭な文章を書く練習にもなった。
必要な場合には、それに製図もつけられた。私がこの製作実習のクラスに出ていた年には、織物と羊毛製品の全工程について学習した。つまり羊毛の洗浄や紡績から布地の仕上げや羊毛製品の光沢仕上げに至るまでである。同様にして帽子や金銀などの貴金属の加工といった家内工業とか、針金製造やモールとか縁飾り加工に至るまでを学習した」
好奇心の目覚め
以上、実科学校の授業についてニコライの生き生きとした報告でお伝えしたが、さらに数学の授業では、機械的な訓練ではなくて、思考の訓練を学ぶことができたという。それはつまり知識の詰込みではなくて、物事の原因と結果について考えさせるという、やりかただったのだ。この原因と結果についての思考訓練は、のちにニコライが歴史の研究に携わったときに、大いに役立ったといわれる。
実科学校でのこのような教授法は、のちにスイスの有名な教育学者ペスタロッチによって形成された「観察こそあらゆる認識の基礎である」という理論を先取りしたものものであったといわれる。こうした状況の中で、少年ニコライの好奇心が、多くの分野で呼び覚まされた。
とりわけ数学の教師ベルトルトから大きな感化を受けた。この教師は生徒の中に、大きな感受性を見出して、数学以外でもニコライを手助けした。一緒になってヴェルギリウスやホラチウスといったローマの作家の古典作品を読んだり、ミルトンの『失楽園』のドイツ語訳を与えて、その語句の美しさにニコライの注意を向けさせたりした。後に彼がイギリス文学に傾倒するようになった、その基盤もこのあたりにあったようだ。
さらにその文章のスタイルを磨かせるために、ベルトルト先生は毎日ニコライ少年に対して、手紙を書かせもした。そして先の孤児院の学校で、宗教というものに懐疑心を抱くようになっていたニコライに、のちに村の牧師になったベルトルト先生は、真の宗教心を目覚めさせたのである。
ところが、おそらくニコライにとって「夢のようであったと思われる」勉学時代は、わずか一年で打ち切られることになった。厳しい父親の有無を言わせぬ命令によってニコライ少年は、現在はポーランドとの国境をなしているオーダー川に面した町フランクフルトの書店に送られることになったからである。今では、フランクフルトというと、国際空港があり、日本人の観光客やビジネスマンにもおなじみの商業都市フランクフルト(アム・マイン)のほうを考える日本人が大半ではないかと思われるが、オーダー川のほとりのこの町は、18世紀には大学もある、かなり重要な町であったのだ。
彼の一生に強い刻印を遺したこの実科学校、とりわけ素晴らしい恩師ベルトルト先生との別れを強制された少年ニコライの心は、「筆舌に尽くしがたい苦痛にみちていた」という。
書店での見習い時代
このフランクフルトの書店でニコライは、1749年から1752年まで、年齢にすると16歳から19歳までの3年間、見習いとして過ごしたのであった。この書店見習いとしての3年間に、ニコライは実科学校で身に着けた勉学の習慣を、さらに本格化させた。
しかしそれはまさに苦学生としての期間であった。父親としては、将来自分の書店を確実に継いでくれる後継者を養成するために、長男だけではなくて、末の弟のフリードリヒに対しても、修業を命じたのであった。その際厳しい家父長であったニコライの父親は、修業中の若者には小遣いを与えず、書店員としての仕事の習得に専念するよう指示した。そのためニコライにとって大学へ進む道は閉ざされたわけであるが、向学心に富んでいたニコライ青年は、まさに疲れを知らぬ熱意をもって、朝の早い時間や営業中の暇な時間を利用して、勉学に励んだのであった。そのころの様子をニコライは、晩年に記した自伝『私の勉学修業時代』の中で、次のように書いている。
「確かに私はそのころ、あらゆる苦労をなめた。冬には大変な寒さにさらされた。店の中も家の中も、部屋は暖房されてなく、夜も朝も明かりというものがなかった。しかし私はこうした苦労を克服することができた。・・・商売上のことには、昼間の三分の二の時間を費やすだけでよかった。そのため余った時間を利用して、あらゆる種類の知識を習得すべく務めた。
私が実行した最初の勉強は、英語の文法書と店の中で見つけた古ぼけた英語の本を頼りに、誰の指導も受けづに英語を学ぶことであった。かなり長い事私は朝食代その他を節約して、照明ランプ用の油を買っていた。それによって私は、冬でも寒い部屋で、朝も夜も勉強できるようになった。夏になってもその節約の習慣は続き、私はミルトンの作品に原文で取り組めるようになった」
勉学修業の継続
こうして彼は独学者の疲れを知らぬ熱意をもって、一歩一歩精神世界へと近づいていったのである。そして様々な領域にわたる彼の傑出した知識の基礎が徐々に形成されていった。新聞・雑誌や、あらゆる種類の書物を手当たり次第に読破していくことによって、のちの彼の博学の基盤が築かれたのだ。
その際かつての恩師ベルトルト先生によって切り開かれたギリシア・ローマの古典への関心は、作家エーヴァルトとの交友を通じて、さらに深まった。当時ニコライはフランクフルト大学の学生たちと知り合ったが、エーヴァルトはそうした学生の一人であった貴族青年の家庭教師をしていたのだ。ニコライは彼から与えられたホメロスのオリジナル版をはじめ、ギリシアの抒情詩人の作品を夢中になって読んでいった。この時以来ホメロスは、ニコライにとって切っても切れない存在になっていくのだ。
さらにニコライは、それまで近づきにくい存在だった哲学も、学生の講義ノートを通じて、瞥見することができた。当時、同大学で哲学を講義していたのは、A・G・バウムガルテンであった。彼は啓蒙哲学者クリスティアン・ヴォルフの弟子で、ドイツ美学の始祖として知られている人物である。独学者のニコライはその講義の一部を盗み聞きするために、教室の扉に忍び寄ったりしたという。そのいっぽう神学の学生パッケと知り合ったが、その講義ノートを通じて、バウムガルテンの論理学、形而上学及び美学を学んだのであった。
これらは全く新しい精神の領域へと彼を導いた。またペスラー教授や法律顧問のフォン・トルといった学識者も、この独学者を受け入れて、その図書室を利用させた。これらの勉学、とりわけバウムガルテンを通じて、習得したヴォルフの哲学から、ニコライは啓蒙思想の豊かな所産を手に入れていったわけである。
しかし学識に対するニコライの姿勢は、大学でのポストを得るために研究を続けている大学教員の細事拘泥主義とは根本的に異なっていて、「現実生活に役に立つか」とか「社会や公共の利益にかなうか」といった基準に基づいていたのだ。つまり彼にとっての学識の意味は、あくまでも社会性、公共性、実用性のはかりにかけられたものであった。こうした基本姿勢をニコライは、すでにこのフランクフルト時代から身に着け始めていたのだ。
これに関連して歴史家のホルスト・メラーは次のように述べている。「ニコライは早い時期から、実生活に即したあり方と実際活動の中での学識とを結び付けていた。彼は前者からは逃れられず、その一方後者なしでは済ますことができなかった。実現不可能な理論を考え出す学者の、誤ってそう思われていたり、あるいは実際に存在する世間知らずな態度こそは、(のちに)彼が哲学論争する時に、(相手を非難する言葉として)持ち出した決まり文句なのであった」
彼が後に信条とするようになったのは、「健全な良識」であったが、そのために彼が身に着けた知識は、あらゆる分野にわたる広範なものであった。それらは、学者・知識人に言わせれば、深く熟考されたものではなく、いわば知識の折衷主義だということになる。しかしそれは死んだ知識ではなくて、社会や公共の役に立つ生きた知識なのであった。その意味でニコライは「象牙の塔」に閉じこもった学識者ではなくて、「生きた社会」のために、その知識を生かそうとした「優れたジャーナリスト」であったのだ。
ニコライが世の中に提供しようとしていたものは、啓蒙の時代にふさわしく、まさに「百科全書的な」知識なのであった。このような姿勢はすでにフランクフルト時代にその萌芽がみられており、そのころ図書館にこもってニコライが考えていたことは、当時の重要な著作家とその作品をまとめて、ある種の事典を作ろうという構想だったのだ。
2 青年時代の活動
ベルリンの実家への帰還
父親の計画では、フリードリヒの書店見習い期間は、1752年の末までであったが、一つには体調を崩したために、もう一つには軍隊勤務から逃れるために、彼はその年の1月にベルリンへ戻り、父親の書店の手伝いをすることになった。ニコライはこの時19歳になっていた。
ところがその数週間後の2月22日に父親が死亡し、その書店は4人の息子たちが所有することになった。ただ書店経営は、長男のゴットフリート・ヴィルヘルムが受け継ぎ、書店見習いをして実務に通じるようになっていたフリードリヒは、全力で兄を助けていくことになった。
そのため彼には、それまでのように勉強していく時間が、ほとんどなくなってしまった。それにもかかわらず、彼は寸暇を惜しんで、勉学を続けたのであった。「朝の早い時間か、夜遅くにしか勉強の時間はなかった。その時間に私は、むさぼるように勉強を続けた。そしてやがて日中にも商売の支障にならないように気を付けながら、本を読んだ。店内の騒音などは気にせずに、読書をしたり、思索にふけったりする術を、身に着けたのである」
やがて父親の遺産をめぐって兄弟たちの間で争いが起こり、結局書店は長兄が単独で受け継ぐことになった。そのためフリードリヒは商売から手を引くことになったが、遺産の自分の取り分とその利子で、質素ながら暮らしていくのに十分な経済的な保証は得られたのであった。
自由の身になって
晴れて自由の身になったニコライは、この後しばらくの間、念願であった学問や文学の研究や、友人たちとの交際に専念できることになった。このころニコライは、ドイツの啓蒙期の最重要な合理主義哲学者といわれるクリスティアン・ヴォルフの教えに取り組むことになった。
「今や私はヴォルフのドイツ語の著作を勉強し始めた。そしてそれを数年間続けた。今や私は、彼の概念規定や彼のとった態度について考えることのできる年齢に達していた。」
ニコライはヴォルフ哲学だけでなく、それまで欠けていた教養を、体系的に身につけようとして、その全エネルギーを注ぐことになった。彼はギリシア語を勉強しなおすと同時に、ヴィンケルマンの著作から刺激を受けて、美術史の勉強にも励んだ。また音楽史の勉強でも、さらに磨きをかけた。以前から和声学を学んでいたが、ビオラ奏者としてもかなりの腕を示した。そのため後年家庭音楽会を開いた時には、ビオラのパートを受け持った。
その一方、この時期に彼は私設図書館の設立も始めている。啓蒙主義の時代は、まさに百科全書の時代でもあったので、ニコライの広範な分野にわたる書籍収集活動は、彼自身の生き方の現れであったのと同時に、時機に叶ったものでもあったのだ。
文芸評論活動の開始
こうした多方面にわたる勉学と並行して、ニコライはすでに執筆活動にも乗り出していた。その手始めとして彼は、学校時代に発見していたイギリスの作家ミルトンの『失楽園』に関する評論を、早くも1753年(20歳)に匿名で発表した。当時ミルトンは、ドイツ語圏の啓蒙の中心地であったライプツィッヒとチューリヒの文芸界で、論争の中心に位置していた作家であったため、この評論は注目を浴びたのである。
その中でニコライはライプツィッヒ在住で、当時ドイツ文学界で帝王と呼ばれていたゴットシェートを批判したのだが、それによってこの人物と対立関係にあったボードマーをはじめとする人々の拍手喝采を浴びたのであった。ともあれこの処女作が文芸界で一定の評価を受けたため、ニコライは自分の作品を公表することに、物おじしないようになった。この時彼は弱冠20歳であったから、書店員としての仕事の傍らに書いたものとしては、かなり早いデビューであったといえよう。
その後ニコライは、当時すでに名声を得るようになっていた作家のレッシングの作品から影響を受けるようになった。レッシングの文体の優雅さと気品が、彼に強い感銘を与えたのである。そしてその軽快な手紙の調子を取り入れて、ニコライは次の作品を1754年にものした。それが『ドイツにおける文芸の現状に関する書簡』で、これは翌1755年に出版された。ニコライの伝記を書いたグスタフ・ジヒェルシュミットによれば、この作品は前述した「ライプツィヒとチューリヒとの間の文学論争に最終的な決着をつけるうえで、少なからず貢献した」という。
ちなみに「18世紀最大の美学論争」といわれている、このミルトンをめぐる争いは、合理主義的かつ擬古典主義的な規範詩学の信奉者たち(ゴットシェート派)と、空想や感情の権利を重視する傾向のあった人々(ボードマー派)との間の典型的な争いであったのだ。またジヒェルシュミットは「この作品の出現によって、ドイツにおける文芸批評不在の時代に終止符が打たれた。ニコライのような、ものにとらわれない、自由な精神の持ち主だげが、名のある人々に対しても批判的に対峙する権利を有した。・・・彼は同時代の、なお地方的なドイツ文学に新たな可能性を切り開くために、両者に対して、容赦ないが、正当だと信じた批判を加えたのである。」とも書いている。
こうしてニコライは文芸評論家としての第一歩を記したのであるが、そこには後年論争家として、様々な論敵と闘っていく自信が、すでにみられるのである。
レッシング及びメンデルスゾーンとの出会い
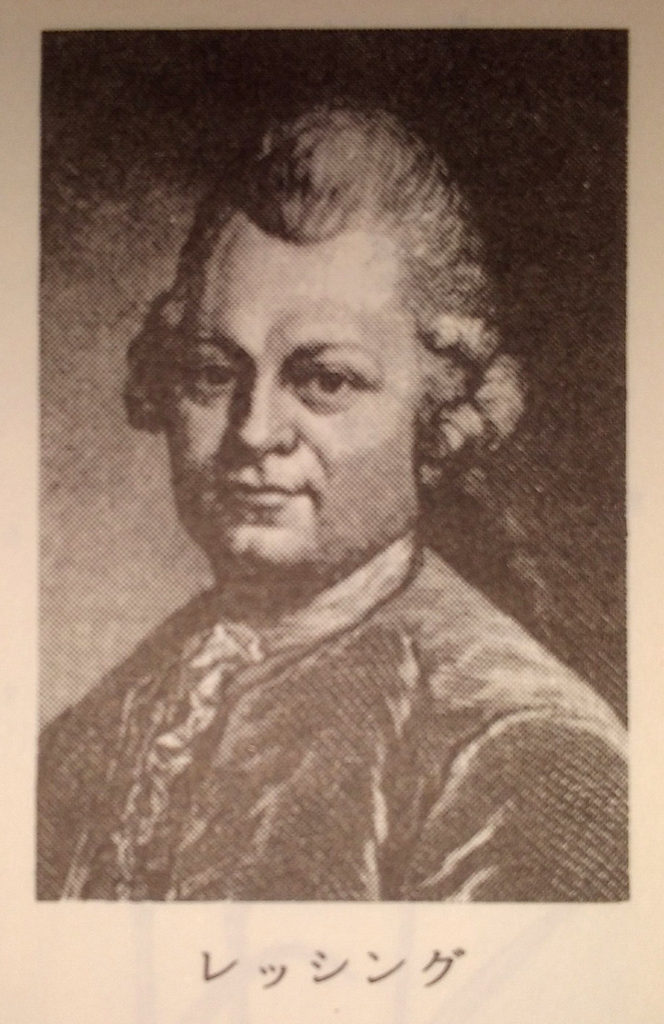
レッシングの肖像
『ドつにおける文芸の現状に関する書簡』は、のちの大作家ゴットホルト・エフライム・レッシング(1729~1781)の注意を引き付けた。その内容に注目したレッシングは、ただちにその作者と知り合いになることを求めた。当時すでに成功した作家となっており、著名なジャーナリストとしても広く世間に影響を及ぼしていた人物が、緊密な精神的な結びつきを求めてきたことは、若きニコライの自尊心を著しく高めた。
彼は他人との精神面での接触や人間的な付き合いというものを常に大切にしていたので、この人物と親しく過ごしたその後の数年間というものは、まさに陶酔的な気分に満たされていたという。収穫の多かったこの時期を振り返って、ニコライは晩年に次のように記している。
「レッシング及び彼を通じて、モーゼス・メンデルスゾーンとも、1755年の初めに知り合った。そしてこの二人と私は親しい友情で結びつけられた。この友情は、これら偉大な男たちの死に至るまで続いた。・・・我々三人は、当時その花盛りの時にいた。真実への愛と熱意に満たされ、三人は何ものにもとらわれない自由な精神のもと、学問上のさまざまな想念を自らの中に育てること以外に、何の意図も持っていなかった。
二十年以上にわたる我々の親密な交際にあって、一度たりとも誤解が生じたことはなかった。我々の会合では、たいていの場合、活発な論争が起こった。しかし互いに何らかの独善的態度や教師面をとることなしに、多くのアイデアが生まれたのである」
レッシングは各地を転々とする定職のない生活を送っていた。しかしベルリンの滞在中には、これら三人の友人たちは、あるいはニコライ家の庭での朝の集いで、あるいはベルリンの有名なワイン酒場「バウマンスヘーレ」での夜の集まりで、親交を重ねていたのである。ニコライはこのころの三人の談話について、次のように書いている。
「レッシングはベルリン滞在中、しばしば我々の哲学談議に加わった。彼がいるとその談義は、一層盛り上がった。彼は議論をするとき、弱いほうに肩入れするか、誰かが賛成論をぶつと、ただちに独特の鋭い調子で、それに反論を加えたからだ。・・・とはいえレッシングのこの流儀は、ただ反論するのが好きだからだというのではなくて、それによって概念をより明瞭にさせようという意図によるのだ」
この時期ニコライは、傾倒していた寛容と自由の国イギリスへ移住して、みじめなドイツから永遠におさらばしようという思いに取りつかれたことがあった。しかしレッシングとメンデルスゾーンとの精神共同体を捨てたくなかったので、結局この考えをあきらめた。この二人と出会った1755年には、ニコライは22歳、レッシングとメンデルスゾーンは26歳であった。
この後三人はドイツの文芸界、思想界に新たな息吹を吹き込む具体的な活動に乗り出すが、彼らは新しい世代感情を代表していたともいえる。これら三人の啓蒙家が作り出した、実り豊かな精神共同体は、ドイツ文化史上これまで以上に高く評価されるべきであろう。
メンデルスゾーンとの交友
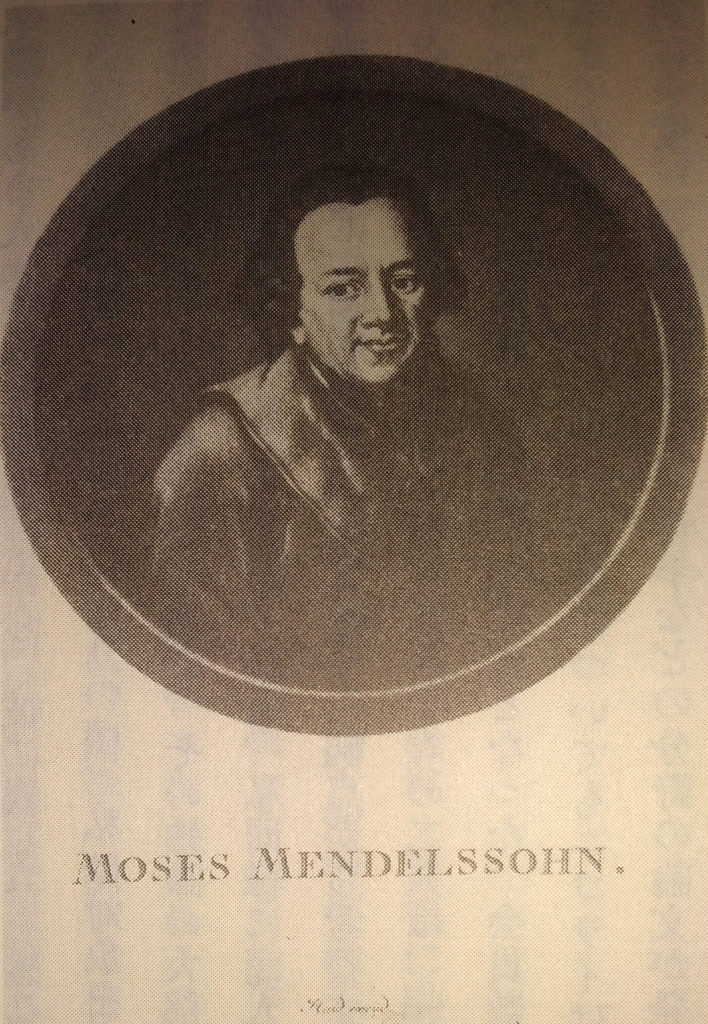
モーゼス・メンデルスゾーンの肖像
モーゼス・メンデルスゾーン(1729~1786)はユダヤ人で、1743年以来ベルリンに住んでいた。その息子は後に、銀行家として経済界で活躍することになり、また孫は日本でもよく知られた音楽家のフェリックス・メンデルスゾーンである。
14歳の時、モーゼス・メンデルスゾーンは、その先生 D・フレンケルがベルリンに新設したタルムード研究のための高校に移るために、生まれ故郷の町デッサウを離れて、プロイセン王国の王都ベルリンにやってきたのだ。当時のプロイセン王は、啓蒙専制君主として知られているフリードリヒ大王(在位:1740~86)であった。この国王はフランスの名高い啓蒙主義者ヴォルテールを呼び寄せるなど、学芸の振興に努めていた。そしてユダヤ人に対しても寛容な態度をとっていたのだ。
さてメンデルスゾーンは生計のために、はじめヘブライ語のテキストを清書する仕事についた。ついで家庭教師をやり、1754年からは絹取引商 I・ベルンハルトの簿記係として働いていた。そして商売に熱心に打ち込み、やがてそこの共同経営者になった。
彼はニコライ同様、大学には行かずにいわば独学で、M・マイモニデス、キケロ、ユークリッド、スピノザ、ライプニッツ、ヴォルフなどの哲学を熱心に学んだ。と同時に数学も勉強し、さらに住んでいた国の言語ドイツ語のほかに、ラテン語、フランス語、英語も習得した。ユダヤ人であったメンデルスゾーンの母語は、西部イディッシュ語であった。
レッシング及びニコライと初めて会ったときは、著作活動を始めたばかりのころであった。後にレッシングはその劇詩『賢者ナータン』の中で、メンデルスゾーンの面影を描き、この人物の姿を後世に伝えている。しかしニコライとしては、同じ商人であり、同時に学識がある人物という共通性から、彼に親しみを感じたようである。この点についてニコライは次のように書いている。
「我々が知り合ったばかりのころ、対象を考察するその仕方において、私はM・メンデルスゾーンに近いものを感じた。なぜなら彼は、その知識の大部分を人から教えてもらったのではなくて、自らの努力を通じて獲得したからである。彼も、私同様に商人であった。そして我々二人は、様々な対象を、もっぱら大学教育を通じて習得した人とは違った観点から考察することを学んだのである」
ニコライとメンデルスゾーンの二人は、1755年、ベルリン在住のミュヒラー教授によって作られた「学識者のコーヒーの会」の会員となった。会員数は百人で、七年戦争(1756~63)の中ごろまで存続したという。そこでは4週に一度、数学、物理学、哲学などの分野の会員の論文が発表されたという。
またこの時期にニコライはレッシングの手引きで、「月曜クラブ」という会にも入っているが、この会については後述することにしよう。
『文芸美術文庫』の発行
休みを知らないニコライは、知識の吸収・習得に励むかたわら、まずは文芸の世界で世の中に働きかけることを始めた。先の文芸批評の中で、彼は「客観的批評ををすべきである」と主張したのであったが、いまやこのことを自ら雑誌を発行することを通じて、実現しようとしたのである。それがつまり1757年創刊の『文芸美術文庫』なのであるが、メンデルスゾーンやレッシングもこの雑誌の発行に賛成してくれた。そしてライプツィヒのデューク出版社が紹介された。
当時のドイツには、医学、法学、神学、歴史学などの専門的な学術雑誌や、人の役に立ち、道徳を奨励することを狙った、一般市民向けの道徳週刊誌などがあった。これらに加えて、1750年ごろのドイツに入ってきて、1780年代にその最盛期を迎えた文芸評論誌が、啓蒙主義のメディアとして、実にさまざまに発行されていた。ニコライのこの雑誌は、いわばそれらの先駆的存在だったのだ。
ニコライはこの文芸評論誌の編集を担当するとともに、その主要な寄稿者としても、まさに水を得た魚のような活躍を示した。彼はドイツ文学のあらゆる分野に目を光らせたばかりでなく、イギリス、フランス、イタリアにおける新刊書をも批評の対象にしようとして探し回った。またニコライはドイツ人の間に文学とよき趣味を育てることを目指して、絵画、銅版画、彫刻、建築、音楽、バレーなどを、考察の対象に含めた。
彼の本質に深くかかわっていた百科全書性が、すでにこの雑誌にも現れたというべきであろう。彼はこの雑誌を一つのフォーラムと考えていたが、その一例として、ドイツでそれまで長年にわたって続いてきた演劇改革に関する議論に対して、この評論誌を通じて決着をつけようと考えたことがあげられる。
そしてそのために第一号で、ドイツで最良の悲劇に対して、50ターラーを授与するという懸賞募集を行った。この募集を通じて、レッシングはその『エミリア・ガロッティ』の構想への刺激を受けたという。そしてそのほか数人の作家が悲劇作品をものしている。ニコライ自身は第一号に、「悲劇について」というエッセイを発表しているが、それに先立って、彼はレッシング宛の手紙の中で、新しい悲劇の在り方について、次のように書いている。
「・・・悲劇の目的は情熱を浄化し、道徳を形成することだという命題を、私は論破しようと思っています。・・・悲劇の目的は情熱を刺激することだと、私は考えます。もっともすぐれた悲劇は最も激しく情熱を揺さぶるものであって、情熱を浄化するものであってはならないのです」
いっぽうこの評論誌を支援していたレッシングは、1757年8月26日付けのニコライ宛の手紙の中で、友人としての率直な忠告を行っている。
「親愛なるニコライ。今回は少しだけにしておこう。私の考えが、いろいろと貴君の気に入ってくれて幸いです。貴君がそこから使えるものすべてを、役立ててください。ただその前に、われらの愛するモーゼスと一緒に考えてほしいのです。というのは、現在私が陥っている混乱した状況の中では、何か役に立つことを考えるのは、ほとんど不可能だからです。
・・・ただ愛するニコライ、誤植が多いのは自分の責任だと思いますか? これからは貴君の原稿は、もう少し読みやすくしてほしいものです。私がそちらにいないと、どんなおかしな誤植が忍び込むやら!・・・お元気で。たびたびお便りを下さい。貴君の真の友、レッシングより」
やがて歳を重ねるにしたがってニコライは、次第に市民的な健全な良識という事を、文学の在り方としても主張するようになっていくが、それは若き文芸評論家時代の考え方とは、著しく異なるものだといえよう。
それはともかく、この文芸評論誌を始めて二年足らずの1758年秋に長兄が亡くなり、ニコライは25歳で出版社の経営を引き受けざるを得なくなった。それを理由にニコライはこの雑誌の編集の仕事を退き、その仕事をヴァイセという人物に譲ることになった。この人物は雑誌の名称を、『新文芸美術文庫』と改めたが、これは1806年まで続いた。
『最新文学に関する書簡』
その後ニコライは商売のために以前にもまして多忙となったが、レッシングの強い勧めもあって、新しい雑誌を、今度は自らの出版社から発行することになった。これが『最新文学に関する書簡』(以下『文学書簡』と省略)で、1759年1月から1765年7月まで、毎週木曜に発行された。今回はレッシングの忠告に従って、ドイツのことだけを扱い、また内容的にも文学だけに集中することになった。「この賢明な自己抑制から、『文学書簡』は驚くべき魅力を発揮して、人の心に強く訴えることができた」という。
文芸批評誌であるのに、文学書簡という名称がついているのは、七年戦争で負傷した友人の詩人エーヴァルト・フォン・クライストに、最新の文学状況を知らせるという形式をとっているためである。プロイセン王国ににとって運命的であったともいえるこの七年戦争(1756~63年)中の高揚した雰囲気が、この『文学書簡』から今日なお伝わってくる。また書簡という形式はこの時代のごく一般的な文学形式でもあったのだ。
レッシングは初期のころはこの雑誌にたくさん寄稿したが、ブレスラウへ移ってからはそれも不可能になった。その代わりに、責任ある編集者としてニコライは、合計335編の書簡のうち64編、つまり五分の一を自ら書いていた。しかしメンデルスゾーンと二人だけでは、この仕事を長く続けられないと感じたニコライは、第8号から常勤の協力者としてトーマス・アプトという人物を迎えることになった。『祖国のために死ぬことについて』という著作によって文芸界にデビューしたアプトは、ニコライにとって頼もしい味方となったのである。
当時のベルリンの文学界の生きた証言になっていたこの『文学書簡』の中では、様々な文学問題が扱われていた。しかしその率直さが、例えば神学に関することでは、正統派神学者の強い反発を呼んだ。その結果この雑誌は一時ベルリンで、発禁処分を受けたりした。
当時すでにニコライは、正統信仰派や敬虔主義者から自由思想家ないし異端者と見なされるようになっていたのだ。そして彼や彼の仲間たちは、侮蔑的に「ニコライ派」と呼ばれていた。このころからニコライは終生、様々な文学上・思想上の敵と立ち向かうことになったわけである。
それはさておきジヒェルシュミットによれば、『文学書簡』は商業的にも成功をおさめ、「今日なおドイツ文学史上に確固たる地位を主張できる」という。そして「そこには文学上の啓蒙主義が高らかに宣言されている」とも彼は書いているのである。またH・メラーも、「・・・文学史的に見れば、(のちの『ドイツ百科叢書』よりも)実り多いものであり、レッシング、メンデルスゾーン、アプトの協力を得て、内容面でも、言語面でも、高い水準にあった」と述べている。
とはいえ、あらゆる困難や停滞にもめげずに、雑誌の発行という事業を推進したのは、ニコライなのであった。啓蒙主義の文学や思想を広く一般に普及させて、ドイツの一般的な文化風土を変革していくことこそ、ニコライがその後終生にわたって、目指したものであった。一般に啓蒙主義の普及に果たした出版業者の役割は大きかったが、出版業者で同時に雑誌編集者でもあったニコライの二重の役割は、格段に評価されてしかるべきであろう。
