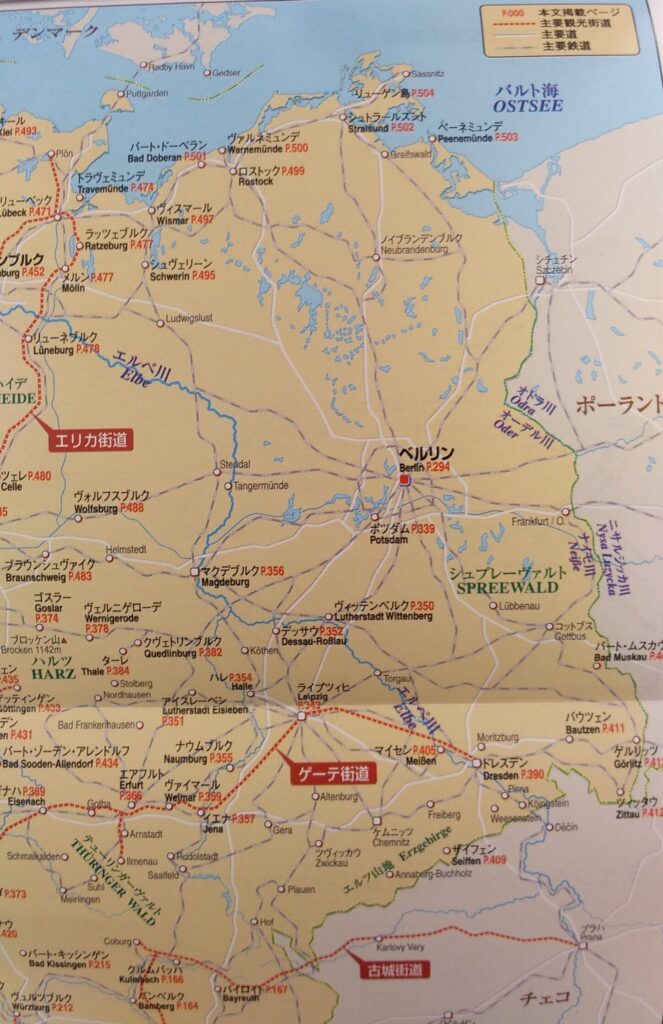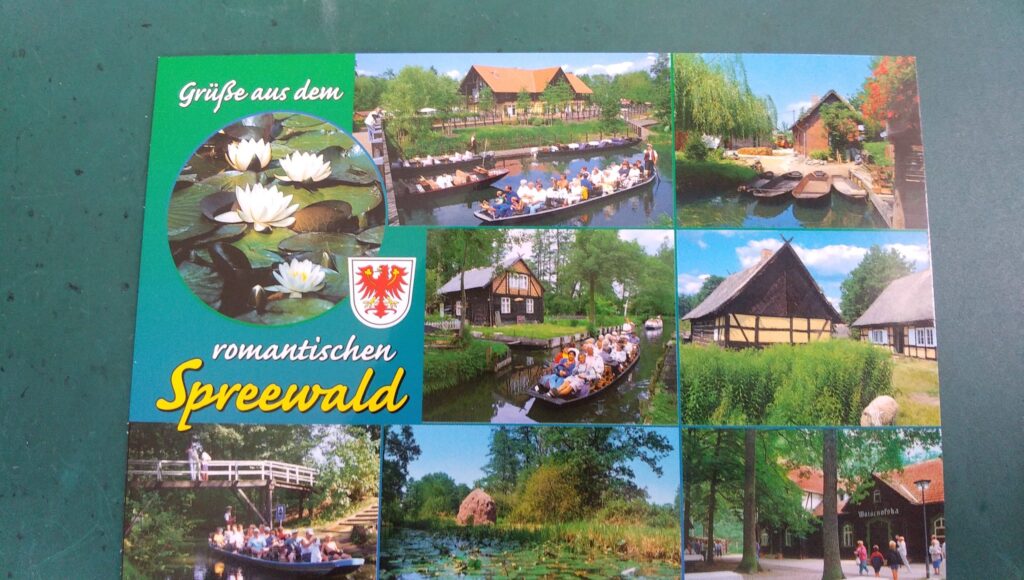第一章 第一次世界大戦と書籍取引
戦時書籍販売の特徴
大戦勃発直以前の1914年6月にライプツィッヒで開かれた、書籍とグラフィックの大規模な国際見本市ブルガは、ドイツの出版界にとって極めて重要な国際的な催しであった。しかしその数週間後に戦争がはじまると、ドイツの出版界と外国の出版界との結びつきは、様々な分野で途切れることになった。そしてまた閉ざされた国内市場の中で、書物の滞貨が次第に進行していった。それは一つには、書物が緊急時には必要のないぜいたく品と見なされたことにも原因があった。戦争が始まって数週間後に、雑誌『鉄道図書販売』の冒頭記事に、「一般庶民は戦時中はぜいたく品は買わないものだ」という内容の文章が載せられた。それが書物を指すものであることは、明らかであった。しかし書物の販売や購読が禁止されたわけではなく、戦場や野戦病院にいる兵士のために、書物が寄贈されたりした。そして占領地にいるドイツ人兵士に対して、鉄道で本を送る「鉄道図書販売」が、この動きに追随した。さらに1916年には、「戦地書店」というものが誕生した。
ここで紹介しておきたいのが、1870年の普仏戦争の時に見られた一つの動きである。家庭向けの人気雑誌『ディ・ガルテンラウベ(あずまや)』の発行人E・カイルはこの時戦地を訪れ、従軍兵士に対して、その予約購読を募ったのである。カイルはこれに関連して次のように書いている。「毎月戦地から『ディ・ガルテンラウベ』に対する注文が山のようにやってくる。戦地で注文する人は軍隊のあらゆる野戦郵便網を使え、しかも予約購読なので、一回ごとに金を送る手間も省ける。一方われわれとしては、戦地を訪れる親類や友人のためにも、注文された雑誌を毎週きちんとメッツやパリへ発送する準備ができているのだ。
戦地書店
これと似たようなことが第一次大戦中にもみられたわけである。つまり1914年レクラム出版社は、その百科文庫を100冊づつまとめて、ひと箱にした「携帯用野戦文庫」なるものを作り出し、戦場、野戦病院、捕虜収容所などへ送ったのであった。そして「ご希望とあれば、寄贈者のお名前を箱の上に印刷して差し上げます」との広告文もつけた。一箱あたりの値段は20マルクであった。一冊当たりにすると20ペニッヒということになるが、この安い値段は19世紀の後半からずっと据え置かれていたのである。ついでに言うと、レクラム百科文庫の人気を逆用して、フランス軍はドイツ軍の指導部やドイツ政府を批判する文章を、レクラム百科文庫の表紙に書いて、ドイツ軍の陣地に投下したという。

携帯用野戦文庫(レクラム)
こうした動きの後1916年になって、「戦地書店」が作られたわけであるが、その許可はたいていは大規模な書店に与えられた。そこで販売された出版物の多くは、やはり戦争に関連したものであった。例えばベルリンのG・ジルケ出版社が長期的に売れ続けるものとして推薦したのは、『三国同盟の刊行物に見る世界大戦の勃発』(30ペニッヒ)であるが、これは10か月で2万6千部売り上げた。また月刊誌の『写真で見る世界大戦』(1冊50ペニッヒ)は1号あたり6万8千部であった。
こうした戦記ものの過剰出版に対しては、すでに大戦勃発直後にも、これを嘆く声が聞かれた。先に「百部刷り」という選ばれた読者向けの豪華本の発行者として紹介したH・v・ヴェーバーは、自分で発行していた雑誌『ごちゃまぜ活字』の中で、そうした書物の内容や質について、手厳しく批判しているのだ。その際彼は一部出版社や書店の金儲け主義を激しく攻撃し、「そうした書店は人々が捜し求めている良質な本を戦地に送るべきなのである」としている。1916年2月のある前線報告にも、「内省的な書物への読書傾向は著しく減っている」と書かれている。
戦争中の書籍販売の実態をもっとなまなましい形で暴露的に紹介したのが、ダダイストのヴァルター・メーリングであった。彼は第一次大戦中の回想録『失われた文庫、一つの文化的自伝』の中で、次のように書いている。「“神われらとともに”とクルップ製の大砲には刻み込まれていた。そして“本を前線に送ろう!”と古典の帯紙に肉太活字で書かれていた。これらの本は、ウールのソックス、救急医療品、戦時チョコレートと一緒に、“野戦郵便-愛の小包”として、わが”勇敢なる若者”のもとに送られたのだ。どの新刊書にも、石炭酸と膿の混じった野戦病院のにおいがしみ込んでいた。そして大本営が戦死者のリストを張り出すように、大出版社は“われらの戦死した作家たちのアンソロジー”を陳列した」
その反面、戦争という特殊な状況の下でかえって人々が読書に目を向けるようになった、という側面があったことも忘れてはならない。このことを実証するいくつかの証言を次に紹介しよう。「戦時中という神経を逆なでするような時期だからこそ、人々は書物の力を借りて、より良きより静かな世界に引きこもる必要性を感じているのだ」、「戦時中、たくさんの兵士だけでなく、一般の人々も読書をすることを知った」、「多くの人々は苦難と危機の時代になって初めて、精神的な道具の価値について目を開いた」、「もし私が自分の本棚の中に1920年代を代表する書物を探すとなると、それは私が第一次大戦中に塹壕の中で過ごした青年時代に読んだ本を取り出すことになろう」、「陣地戦は数多くの新しい読者を生み出した。そして戦争の終わりごろには、いくつかの出版社の倉庫は空っぽになっていた」
これらの証言でも分かるように、長い塹壕戦の続いた第一次大戦の前線で、兵士たちは読書をする時間が十分あったわけである。陸軍中尉として従軍していた出版主のH・ベックは、ある戦地書店でシュペングラーの『西洋の没落』を見つけてこれに注目し、戦後自分の出版社からこの本を出版して大成功を収めたという。
紙の管理統制
戦争は一般的に言って、物の生産に有無を言わせぬ影響を及ぼした。とりわけその影響は戦後になって恐ろしいまでに現れた。出版業界に対しては、紙の管理統制による生産減少が悪影響を及ぼした。製紙に関する統制は、大戦中の1916年6月20日に告示された。そして書物は1920年10月1日まで、新聞は1921年4月1日まで、統制経済の下に置かれた。こうした経済的困難の中で、出版社と書店との間の利害の対立があらわになってきた。そして書籍販売業者は自らの利益を護るために、独立した組織づくりを始めるようになった。こうしてベルリンの書籍商ニッチュマンのイニシアティブによって、1916年5月19日に、「書籍商ギルド」が結成された。これは1886年に設立された出版主協会に対抗する形で作られたものであった。しかしこうした動きにもかかわらず、出版界全体の組織である「ドイツ書籍商取引所組合」は存続した。
出版社と書籍商の間の紛争の主たる対象は、物価上昇に伴うものであった。販売業者としては利益を確保するために、各種の割引を廃止したいと考えた。こうして年間予算が1万マルク以下の図書館に対して、プロイセン文部省が1903年に許可した割引を放棄することに、「書籍商ギルド」は成功した。この措置はドイツの他の地域でも相次いで実行されることになった。
しかし戦争による一般的な物価上昇は、さらに出版業界全体に物価上昇割増金の導入をもたらした。つまり書籍の定価を一定率値上げしたのである。これは大戦末期の1918年春に開かれた「書籍商組合」の総会で決議されたもので、ドイツの書籍販売業界のあらゆる分野に拘束力をもって適用されることになった。ただしこの時はプロイセンの図書館及び官公庁は除いて、10%の割増金が決定された。そして1920年1月になって、この割増金は10%から20%に引き上げられた。ただし専門的な学術書の出版社はこの決定に従わずに、10%の割増率に固執した。このような混乱を経て、この割増率は1920年10月には再び10%に引き下げられた。
第二章 インフレの時代と1920年代
インフレーション
1918年11月に第一次大戦が終了した後も、敗戦国ドイツの物価はじりじりと上昇の一途をたどった。そして通貨暴落の速度は、1922年の後半に入るとどんどん上がっていった。やがて出版界としても書物の値段を、従来の物価上昇割増率では調整することができないほどに、貨幣価値の下落の速度は激しくなった。「書籍商組合」としては、出版物の基本価格を何倍にしたらよいかというキー数字を「取引所会報」に発表することによって、このインフレに対応した。その度合いがいかに激しいものであったか、次に見てみよう。1922年9月13日には、キー数字の倍率は従来の60倍になった。そして12月27日には600倍に、1923年6月21日には6300倍に、8月11日には30万倍に、9月7日には240万倍に、11月20日には6600億倍に、そして11月22日にはついに1兆1000億倍にも達した。この時点になってドルを基軸にしたレンテンマルクが導入されて、これによってこの気ちがいじみた狂乱インフレはようやく終息したのであった。
その2週間後の12月5日には、「書籍商組合」もキー数字による勘定を取りやめることにした。紙屑同然になった紙幣の山を大きなリュックサックに詰め混んで、買い出しに出かけたといわれるほど、ドイツ人の心に暗い影を落とした狂乱インフレではあった。今度はこれを本の値段で具体的に見てみることにしよう。例の人気ナンバーワンの「レクラム百科文庫」は、1867年の創刊以来1917年まで半世紀にわたって、1冊の値段が20ペニッヒに据え置かれていた。それから装丁などを改善して25ペニッヒとなり、この値段がしばらく続いた。ところがインフレの終末期には、その1冊の値段は何と3300億マルクにもなっていたのだ。
この狂乱インフレのあおりを受けて、古くから続いていた名の通った老舗の出版社が、数多く倒産した。またこのインフレのために条件販売取引や委託販売取引がなくなり、出版社との直接取引(しばしば前払いで)が主流となった。いっぽうドイツで出版された書物の外国への輸出は、戦争中はほとんど壊滅状態になっていたが、戦後になって徐々に回復し始めていた。ところがドイツの通貨大暴落によって、書物の輸出は今度は極端なまでに増進することになった。それはバナナのたたき売りよりはるかに悪い、本の投げ売りといった感を呈していた。これによってこの時期ドイツの貴重な書物が洪水のように外国に流出したといわれている。
この頃(1923年=大正12年)ドイツに留学していた日本人の学者や本好きのパトロンが、ドイツ語の貴重な文献資料や出版物の数々を、ごく安い値段で大量に日本へ持ち帰ったというエピソードがいくつも残っているぐらいなのだ。
その後の出版業界の動き
さしもの狂乱インフレも1923年末の「レンテンマルクの奇跡」によってぴたりと終息し、ドイツの社会も1929年末の世界大恐慌の発生まで、つかの間の安定期を迎えた。1922年ライプツィヒの出版主ローベルト・フォークトレンダーの提唱によって、書籍取引の根本的な合理化措置として、「書籍商精算協同組合」なるものが設立された。しかし発足早々に狂乱インフレの強烈な打撃を受けて、この組織もしばらくは開店休業の状態に陥った。とはいえ経済情勢の安定化に伴い、この協同組合は徐々に活動を再開し始めた。これは清算取引を中央に集中することによって、簡素化することを狙ったものであった。従来は数多くの出版社とその得意先の間で、個別的に勘定取引が行われていた。それを一つのセンターに集めて、請求業務と支払い業務を行い、同時に配分比によって受け取り手に渡すというものであった。このようにして数多くの帳簿記入をやめて、一回の帳簿記入で間に合うようになったのである。この「書籍商精算協同組合」は、1842年のフライシャーによる「ライプツィヒ注文センター」と同じ考えに基づくものであった。
いっぽう「ドイツ書籍商取引所組合」は1923年に、宣伝広告部門を作った。そしてその二年後の1925年には、組織内部の争いや経済的困難にもかかわらず、その創立100周年記念行事を大々的に祝うことができたのである。またG・メンツ博士によって、ライプツィヒ商科大学内に、書籍取引経営学講座が作られた。さらに狂乱インフレによって吹き飛んでいた書物の定価制度も、その後の安定期に再び採用されるようになっていった。そして1928年には、9000の書籍販売業者と1100を超す出版社の間の取り決めや「書籍商組合」の新しい規約の導入などによって、ドイツの出版業界は再び新たな基盤を獲得した。しかしそれは社会や文化の他の多くの分野と同様に、ドイツの出版業界にとっても、「つかの間の安定期」にすぎなかったのである。
1929年末の世界大恐慌の影響を受けて、売り上げ減少と資本不足、大幅な生産減退と支払い不能といったもろもろの事態に、ドイツの出版業界も陥った。こうした困難は、諸官庁の文化予算の大幅な削減措置によってもたらされた面も少なくない。「書籍商組合」はこうした措置に対して何度も抗議を行ったが、効果はなかった。
出版人養成機関
1920年代の初め、専門的な職業機関としての出版人の養成機関設立の動きが活発になった。これは当初、世紀転換期の代表的出版人の一人であるオイゲン・ディーデリヒスの働きかけによって動いた。その目的は将来の出版人を育てるための職業訓練を、出版界内部の独自の機関で行うというものであった。彼がこれを思いついたのは当時盛んとなっていた青年運動であったというが、何よりも戦後ドイツの出版界が陥っていた窮状が、ディーデリヒスを動かした原動力であった。
1923年、ディーデリヒスは「取引所会報」に一つのアピールを発表したが、それは『変わらねばならない。ドイツ出版界への挑戦状』というタイトルのものであった。これに対する具体的な反応として、ラウエンシュタインで第一回の会議が開かれた。その後の動きは順調で、やがて出版人の養成機関「ユング・ブーフハンデル」が設立された。その活動は多岐にわたっていたが、新人に対して集中的な職業訓練をまず施した。それは夏の合宿コースや職能向上のためのもろもろの研修などであった。今日のドイツではこうした職業訓練や研修は当たり前のことになっているが、当時としては新しい試みであったのである。そしてこうした職業訓練の法制化の考えが、1927年に「タウテンブルク決議」の形で採択されたのであった。しかしこの未来の出版人の養成所は、1933年ナチス政権の誕生とともに幕を閉じることになった。
ブッククラブ
ドイツでは第一次大戦後になって大きな社会変動が起こり、戦前の中流市民階層が没落し、貧窮化することになった。この市民階層こそは書物の潜在的な読者であったのだが、戦後はこの階層の人々にとっても書籍は高いものになった。こうした変化に応じて勢いを増してきたのが、「ブッククラブ」の制度であった。これは出版社が本の買い手を会員の形で確保し、その会員に一般の定価より安い値段で、選定した出版物を届けるという制度である。
この「ブッククラブ」は第一次大戦後に初めて現れたものではなく、その最も初期の形態は1872年に生まれている。この時はクラブの経営者は書籍販売業者と提携したが、出版社側からは激しく攻撃されたという。次いで1891年には、労働者の教育向上の観点(”知識は力なり”とか”書物を民衆に!”といった掛け声とともに)から、「書物の友の会」というものが作られた。その後出版社の中にも、ブッククラブに関心を示すものが出てきた。例えばフランク出版社は自然科学の知識を国民に普及させることを目的に、ブッククラブ「コスモス」を設立した。さらに1916年には「ドイツ店員同盟」が、「ハンザ出版協会」と提携して、「ドイツ国民文庫」を創設した。これらの組織はすべて、労働者や手工業者、店員といった一般民衆の成人教育を狙って作られたものであった。
ところが第一次大戦後に生まれたブッククラブの会員には、いま述べた下層の人々だけではなくて、戦争とインフレで貧乏になった市民階層も含まれるようになった。いっぽうでは戦前の古き良き時代の出版人であったS・フィッシャーのように、20年代の半ばに「書籍市場における異常な静けさ」(1926年)を口にする人もいた。フィッシャーはさらに次のようにも言っている。「人々はスポーツをしたり、ダンスをしたり、夕べともなればラジオを聴き、映画館に行く。仕事のほかに人々がすることは沢山あり、本を読む時間などありはしないのだ。」
たしかに第一次大戦後、ドイツは大衆社会化し、人々の生活行動も戦前に比べてはるかに多様化した。しかしだからといって人々が全く本を読まなくなったのではなくて、実際には読書の形態も書籍販売の形態も多様化したのであった。その一つがここで取り上げているブッククラブというわけである。1924年にライプツィヒに「本のギルド・グーテンベルク」が、ベルリンに「ドイツ書籍協会」の二つが設立された。前者は元来印刷工見習い組合が作ったものである。次いで1925年には「福音派ブッククラブ」と「ボロモイス協会ブッククラブ」が、1926年には社会主義的傾向の「ビュッヒャークライス」が、そして1927年には「ドイツ・ブッククラブ」が生まれたのである。ブッククラブは元来会員に対して、配給するすべての本について予約購読制をとっていた。しかし先の「ドイツ書籍協会」の場合は、提示した本の中から年間70~80点を選ぶことができた。また「福音派ブッククラブ」の場合は、会員以外にも、値段を高くして、一般書店を通じて提供していた。
学術図書館への財政援助
第一次大戦を通じてドイツは諸外国と各方面で交流を欠くことになったが、外国書の文献もこの間ドイツに流入しなくなった。そのためこうして生じた外国語文献の調達を図ることを目的として、F・S・オットーのイニシアティブによって、1920年に「ドイツ学術支援組織」なるものが創設された。その基本理念は「世界中で出版された学術図書の中の重要なものは、ドイツ国内のどの図書館にも少なくとも一冊は備えておくべきである」というものであった。つまりどんな地域に住んでいる人にも、そうした書籍文献に容易に接することができるように、という分散的収集の考え方なのであった。
と同時に図書館相互間の貸出交流の活性化も図られた。この考え方のモデルは、二十世紀の初めにアルトホフがプロイセン学術図書館のために実現したものであった。「ドイツ学術支援組織」は1920~1932年の間、各地の図書館の外国書収集のために、総額870万ライヒス・マルクを支払った。そしてその調達に当たっての実際の業務は、国立図書館交流機関と共同で行った。
ところが1929年の世界大恐慌のあおりを受けて、「ドイツ学術支援組織」の予算は削減され、やがて全面的に撤廃されることになった。その結果、例えばテュービンゲン大学では、1931年には一度に530種類の雑誌が削られ、その続きのものは当分の間調達されないことになったのである。一般に文化予算は経済危機の時代には真っ先に削られる傾向があるが、この時の措置もまさにこの原則が当てはまったのである。この経済危機の時代、ドイツでは出版社や書店の多くが倒産した。このことは『書籍取引所会報』に、出版社などの和議や破産申請が、再三再四にわたって、掲載されたことからも分かるのである。