人気小説『学士ゼバルドゥス・ノートアンカー氏の生活と意見』
この人気小説の概要
多彩な才能の持ち主であったフリードリヒ・ニコライは、人気小説や他人の小説のパロディー作品もいくつか書いた。なかでも小説『学士ゼバルドゥス・ノートアンカー氏の生活と意見』が、この分野での彼の代表作であった。これは1773年から1776年にかけて、ニコライ出版社から三巻本として順次刊行されたもので、三巻あわせて716頁の長編である。現在ゲオルク・オルムス出版社から発行されているニコライ全集の第三巻に、オリジナルのまま収められている。またドイツの「レクラム百科文庫」にもおさめられ、今日なお大勢の人が読める状況にある。
さて1773年春にこの小説の第一巻を発表したが時、ニコライはそれまでの文芸評論よりも広い文学の世界に、第一歩を記したといえる。当時の最も緊急なテーマに敢然と挑んだ、この作品はただちに大きな評判を呼んだ。1799年までに四版を重ね、総発行部数は一万二千部に達した。この数字は現在の基準からすれば、微々たるものに見えようが、当時としては十分ベストセラーに数えられるものであったのだ。この数字はニコライ出版社からの正規の分だけであるが、当時は人気作品の翻刻版(いわゆる海賊版)が当たり前であったことから、この小説の海賊版が三種類、そして模倣作品が数種類刊行されている。さらにやがてフランス語、英語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語に翻訳出版されている。これらのことを考えてみれば、この人気小説がいかにもてはやされたか、分かろうというものである。
成功の秘密
『ゼバルドゥス・ノートアンカー』の成功の秘密は、とりわけこの小説の中に、当時のドイツ人の生活ぶりが説得力をもって描かれていたことにあった。その意味でこれはドイツ初の写実小説といわれているのだ。作家のヴィーラントは『ドイツ・メルクーア』誌の中でこれを知ったとき、思わずこれに拍手喝采したといわれる。また啓蒙主義の仲間であったボイエはこれを、「ドイツ最初の長編小説である」と称えている。そしてドイツ人作家がやっと外国の模範から解放されて、生活の実態に即したドイツ人の性格を描いたことは、歓迎すべきことであると、人々は感じたといわれる。実際そこには18世紀ドイツ社会の様子が生き生きと描かれていて、われわれがその時代を知るうえでの貴重な社会史の史料にもなっているのだ、
ただその文学的な評価には問題があるものの、これを高く評価する人もいる。「ニコライの文章は軽妙で明晰であったが、ややドライで、単調であった。しかしその文体は前時代の古臭い散文に比べれば、はるかに進歩したものであった。そこにはレッシングの厳しい教えが守られていて、小説全編をつうじて、レッシングの息吹が漂っている」とまで、ニコライ研究者のジヒェルシュミットは書いているのだ。
しかしニコライ自身は若き日の文学評論活動を経て、この小説執筆に至った四十歳のころには、純粋な意味での文学的ないし美学的な面での質的向上よりは、当時のドイツ社会の実態や弊害などを、小説という手段を通じて人々に伝え,警鐘を鳴らすことの方に、より強い関心を向けていたといえる。その結果この小説の中には、強度の啓蒙主義的傾向がみられるといわれているわけである。
それにもかかわらず、この小説は決して無味乾燥なものではなく、そのストーリーの展開と数多くの興味深い細部描写に、同時代の人々は魅了されたのであった。ニコライは大変器用な人間で、その啓蒙的な意図を生の形で伝えるよりは、小説仕立てにした方が、より効果的であることを十分心得ていたように見受けられる。そのため災難、強盗の出現、船の難破、決闘、誘拐といった冒険小説の諸要素を、巧みに調合して利用したのであった。
またニコライは強い諷刺精神の持ち主でもあったので、この小説の中でも諷刺の笑いを通じて読者を説得し、状況を改善しようとしたわけである。ともかくこの小説は上質な娯楽小説の要素を持っていたため、当時の人々の人気を博したのであったが、ニコライは一体どこからそうしたものを学んだのであろうか。
まず一見して分かることであるが、この小説の『・・・・の生活と意見』という表題は、18世紀イギリスの作家ローレンス・スターンが、その少し前に発表した『紳士トリストラム・シャンデイ氏の生活と意見」からきている。またニコライの諷刺の笑いも、スターンのこの小説に通じるところが少なくない。例えば主人公のノートアンカーが馬鹿みたいに黙示録を勉強するのも、スターンの小説に見られる奇癖の数々の影響ともいわれる。とはいえニコライの諷刺精神は決して借り物ではなく、その確かな観察眼、ユーモア、自己に対する皮肉などは、文章表現上の欠陥を補って、彼の長編小説の長所となっている。
いっぽう登場人物の選択や筋書きにヒントを与えたのは、同時代の作家M・A・v・テュンメルが1764年に発表した人気小説『ヴィルヘルミーネあるいは結婚した細事拘泥者』であった。この小説は18世紀に流行した、例の「道徳週刊誌」に掲載された小説が用いていた常套的なトリックを使って一定の読者を確保していた。ニコライもこれに倣って、いわばその続編として『ノートアンカー』を書いたともいわれている。
小説のテーマ
ニコライのこの小説は、当時のドイツ社会の実態を写した鏡であったのだが、そこに写し取られたものは、まず何よりも社会に根強くはびこっていた宗教的慣習であった。実際にニコライは、この小説の中で、その時代に活発に展開されていた宗教論争に具体的に介入した。その際彼は、なお根強く残っていた迷信、精神的隠ぺい、信心家ぶり、宗教的不寛容などの実態を暴き、それらと断固闘う姿勢を見せている。後にニコライは南ドイツ地域を旅行して、そこで行われていたカトリック信仰の実態を親しく見聞して厳しく批判したのだが、この小説では彼自身が住んでいた東部および北部ドイツで行われていたプロテスタント信仰の実態を弾劾したわけである。
周知のように、16世紀前半に行われた宗教改革によって、ドイツの社会はカトリックとプロテスタントの両勢力に大きく分裂し、苛烈な宗教戦争にまで発展した対立抗争を繰り返していた。そして同じプロテスタントの中でも、ルター派正統主義、敬虔主義、カルヴァン主義等に分かれ、それぞれが地域的に細分化された領邦君主その他の世俗勢力と密接に絡み合って、18世紀後半になってもなお総体として地方ごとの狭い視野に閉じこもった状況を作り出していた。
ニコライの啓蒙主義が目指したのは、一言で言えば、脱宗教支配の近代社会の実現であったが、その当面の敵として攻撃の矛先を向けたのは、宗教的過激主義の代表としての敬虔主義とルター派正統主義なのであった。具体的には例えば、地獄の劫罰の教えといった、理性的解釈からは逸脱し、近代の世俗化した人間にとってはほとんど受け入れがたい、個々のドグマと闘ったのである。
またニコライは当時のドイツ社会に見られた別の側面にも目を向け、痛烈に批判した。例えばドイツ人貴族の様々な弱点や、地域ごとに散在していた彼らの宮廷生活に見られた愚かしい風習などを、批判の矢面に立たせたのであった。つまり彼らの贅沢三昧で自堕落な生活ぶり、浅薄な行動、身分上のうぬぼれ、腹立たしいフランスかぶれ、さらにドイツ語・ドイツ文学の軽蔑やドイツ人としての国民感情の欠如といったことを、持ち前の諷刺と皮肉を交えてこきおろしたのである。これはドイツ人の一般読者に対して、少なからぬ効果を上げたといえる。その際ニコライは返す刀で、役人たちの卑屈な態度も弾劾してやまなかった。
この小説のもう一つの特徴は、登場人物の中の幾人かを、実在の人物を戯画化した形で登場させていることである。そのパロディー化された人物は、当時の教養人にとっては、誰であるのかすぐに見分けがつくような人物だったのだ。そのため小説発表の後、いろいろ物議をかもした。
物語の筋書き
さてここで長い物語の筋書きを、できるだけ要領よく紹介することにしよう。主人公の名前はゼバルドゥス・ノートアンカーといい、大学出の学士であったが、中部ドイツ、チューリンゲン地方の村の牧師として、長年村人たちの尊敬を集めていた。そしてドイツのある地方君主の宮廷で宮仕えをしていたヴィルヘルミーネを妻に迎え、子供もでき、幸せな結婚生活を送っていた。
ところが六十歳という老境に達したとき、ルター派教会の管区総監督で上司にあたる人物と、神学上の見解を巡った議論に巻き込まれる。主人公は長年真摯に神学研究を行ってきたのだが、この時いわゆる地獄の劫罰期間の問題で、上司と対立した。村の牧師は、「神の善意に限度を設けるのは、人間にふさわしくない」といったのだが、これに憤激した上司は、「神を信じぬこの男は信仰の基本原理に反した主張を行ったのだから、牧師の地位をはく奪されるべきだ」と述べた。
そして正直そのもので、世間知らずの牧師は数時間のうちに牧師館を立ち去るよう命令された。そして所用で留守中に彼の家は他人のものになり、妻と赤子の末娘は別の小さな小屋に移された。運悪くその妻と赤子は病の床に伏していたが、この騒ぎがもとで死んでしまった。

挿絵(病の床に臥すノートアンカーの妻と赤子)
そして家と妻子を失ったゼバルドゥス・ノートアンカーは故郷の村を離れることになった。彼にはもう一人息子がいたが、兵役にとられてこの時不在だった。また長女のマリアンネはある身分の高い夫人のお相手役として、やはり故郷を離れていた。
続く第二章では、主人公は友人で書籍商のヒエロニムスから、ライプツィッヒの印刷所の校正係の仕事を世話してもらう。この書籍商はその際世間知らずの主人公に、ドイツの書籍出版業界の実情について詳しく説明している。しかしやがて意地の悪い者たちによって校正係の職を奪われる。そのため主人公はライプツィッヒを離れたが、ふとしたことで知り合った陸軍少佐の紹介状を携えて、プロイセン王国の王都ベルリンへ向かうことになった。郵便馬車に乗って旅立ったゼバルドゥスは日が暮れてから、とある森の中で強盗の一味に襲われ、頭を殴られ意識を失った。翌朝意識を回復したとき、彼は傍らに御者が死んでいるのを見た。彼自身は上着をはぎ取られ、わずかな小銭を遺して金と紹介状も奪われていた。しかし生来楽天的な主人公は、自ら研究を深めていた黙示録の言葉に励まされて、いずことも知らずに歩き出すところで第二章が終了している。
第三章では一転して、ゼバルドゥスの長女マリアンネの物語となる。彼女は書籍商ヒエロニムスの仲介で、身分の高いフォン・ホーエンアウフ夫人のお相手役となるのだ。マリアンネのフランス語の能力が証明されて、晴れて彼女はこの貴族の家に入ることができたわけである。当時のドイツ人貴族の間では、フランス語が常用されていたからである。
このマリアンネは物語のもう一人の主人公として、とりわけ女性読者の関心を狙った恋愛小説仕立ての中で活躍するのだ。と同時にニコライは、もともとは市民身分から成りあがったフォン・ホーエンアウフ一家の、虚飾に満ちた贅沢三昧の生活ぶりを、その独特の諷刺をきかせて描くことも忘れていない。
さてマリアンネがこの家に来て三か月したとき、フォン・ホーエンアウフ夫人の甥にあたる若い男がこの家にやってきた。彼は織物商人の息子で大学生であったが、柔弱な文学青年であった。ニコライはこの男にわざわざ「ゾイクリング(赤ん坊)」という名前を付けているが、これは同時代の作家ヤコービを戯画化したものであった。思考力が弱く、甘い感傷に熱中し、当時その名声も消え失せていた、この作家へのあてこすりや風刺は実に巧みである。
この文学青年はこの家の社交の場で、マリアンネの存在を知る。そして黒髪で青い眼、美しい顔立ちをした娘が良い趣味を持っていて、自分の朗読した詩に心から賛同するのを見て、マリアンネに恋心を抱く。彼女の方もこの母性本能をくすぐるようなところがある男から、はっきり美しいといわれて彼を好きになる。こうして彼らはフォン・ホーエンアウフ家の庭を散歩したりしながら逢引きを重ねた。しかしふとしたことから夫人の知るところとなり、甥と侍女とが交際するのを嫌った夫人は、結局マリアンネを夫人の知り合いの某伯爵夫人のところへ追いやってしまう。
第四章は再びゼバルドゥスの物語となる。彼は強盗に襲われた後、行方も知れぬ旅を続けていたが、その途中一人の男と知り合う。この旅人はベリリンへ向かうところだと聞いて、ゼバルドゥスは同じ目的地まで旅の伴侶ができたことを喜ぶ。この男は敬虔主義の信奉者で、強盗に襲われたことを話したのがきっかけで、二人は神や宗教を巡って議論を始める。敬虔主義に批判的なニコライはここで、その性善説が実は欺瞞に満ちていることを、様々な実例を通して暴いている。
しかしいろいろな経験をした後、ある日曜日の午後、二人はやっと目的地のベルリンにたどり着く。そして二人は西部の郊外に広がっている広大な公園「ティアガルテン」に足を踏みいれる。そこで展開されている日曜日の午後の活気に満ちた光景に関する描写には、なかなか捨てがたいものがある。ところが道連れの敬虔主義者は、「都会はソドムとゴモラのようだ」として、ベルリンの喧騒を忌み嫌う態度を示し、二人は別れることになる。
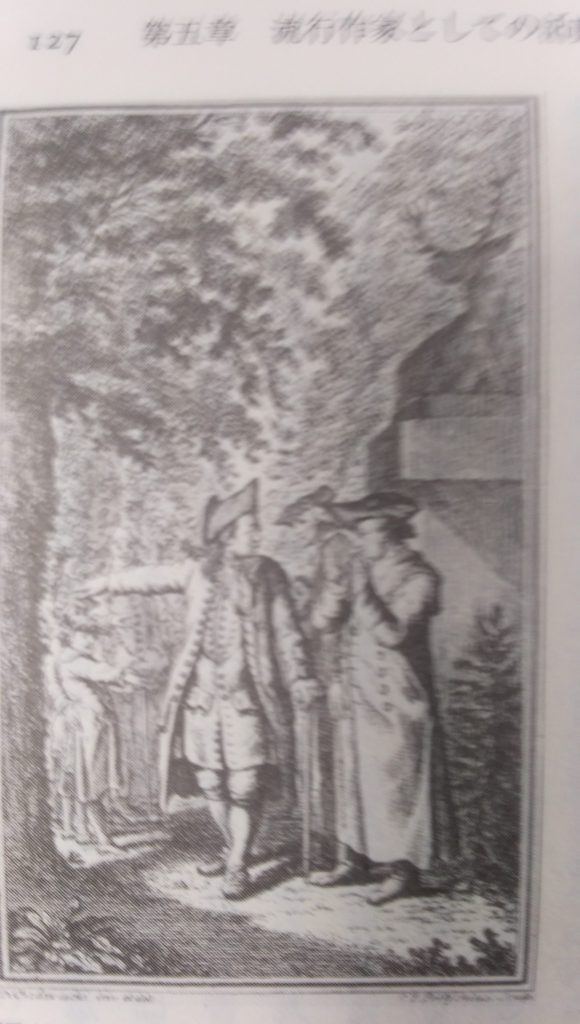
挿絵(ティアガルテンでの一場面)
ゼバルドゥスは乞食のような哀れな姿となっていたが、ふとしたことから学校の校長と知り合い、その家に温かく迎えられる。そしてそこの家の子供たちにピアノを教え、併せて楽譜を写す仕事にありつく。またこのベルリン滞在中、主人公はF氏と知り合い、その身の上話を聞くが、この人物もゼバルドゥスと同じように、聖職者の不寛容と暴力の犠牲者であることを知る。F氏と主人公はシュプレー河畔を散歩しながら、宗教的不寛容が人々の実生活に及ぼしている弊害などをめぐって、いろいろと話し合う。
その後ゼバルドゥスは長い間娘のマリアンネの消息を知らなかったこともあり、ベルリンを離れ、友人のヒエロニムスを訪ねることになる。そこでヒエロニムスは主人公のために、あらたにホルシュタイン地方の図書館の司書の仕事を斡旋することにして、一通の推薦状を書く。絶えず各地に所要のあった書籍商のヒエロニムスは、この度もマグデブルクに用事があるというので、二人は郵便馬車に乗り、途中まで旅を共にすることになる。その途上、馬車の行く手に大声が上がり、何か出来事の発生を予感させるところで、第四章が終わっている。
第五章は再びマリアンネとゾイクリングをめぐる物語となる。その後マリアンネは某伯爵夫人に温かく迎えられ、彼女の屋敷で幸せに暮らすことになった。この章では新たにゾイクリングの家庭教師ランボルトという若い男が登場する。マリアンネと引き離されてからも彼女への思いを忘れることができなかったゾイクリングは、この家庭教師に何とかして彼女の消息をつかんでくれるよう頼みこむ。ランボルトはやがて彼女の消息を知り、一計を案じてマリアンネを誘拐することに成功する。
馬車に乗せられた彼女は逃亡の機会を狙っていたが、ちょうどそこへ通りかかった郵便馬車の姿を見つけたマリアンネは、勇敢にも馬車から飛び降りた。その時あがった叫び声を、第四章の終わりでゼバルドゥス一行が耳にしたわけである。こうしてマリアンネは長いこと離れ離れになっていた父親とヒエロニムスに偶然、再会することになった。このようなストーリー展開は、まさに大衆小説の常套手段であるが、それはともかく父と娘は抱き合ってその再会を、心から喜んだ。ところがその再会の喜びもつかの間、ゼバルドゥスは娘とヒエロニムスの眼前から消えてしまう。
第六章では、二人と別れた主人公のその後が語られている。単独で馬に乗っていたゼバルドゥスは自分の研究テーマである黙示録のことに没頭している間に、道を間違えてしまったのである。しかしヒエロニムスが書いてくれた推薦状とたっぷり残っていた路銀に安心した主人公は、何とか目的地のホルシュタインにたどり着き、お目当ての宮廷侍従に会うことになる。当初目指していた図書館司書のポストには既にほかの人が就いていたため、ある牧師の息子の家庭教師の職で我慢することになる。
ところがゼバルドゥスはこの牧師とも、宗教上の見解を巡って対立することになる。その際主人公は次のように自説を主張した。「上位の聖職者の要求に盲目的に従うことは、プロテスタンティズムの真の精神に反することです。我々が信仰すべき教えについて、我々は納得していなければなりません。それが聖書であれ、信条書であれ、その他のものであれ、ある本に書いてあるからと言って、それを盲目的に受け入れることは、納得したことにはなりません。真実についての理性的な探求を通じて我々が納得したときにはじめて、道徳的な効果を発揮できるのです。」ここには啓蒙主義者ニコライの宗教観が、主人公の口を通じてそのまま示されているといえよう。
このように自己の信念に忠実なために、行く先々で衝突を繰り返していた主人公であったが、息子の消息は長い事途絶え、せっかく再会した娘とも離れ離れになり、その日々はみじめになっていた。そうした生活に倦みつかれた主人公は、遠く海のかなた東インドに行ってしまおうと決意する。そして東インドへの出発基地であるアムステルダムへ向けて、北海に臨む北ドイツのクックスハーフェン港を船出するところで、第六章が終わる。
次の第七章では、主人公は様々な運命のいたずらにもてあそばれ、波乱万丈の体験を重ねることになる。ゼバルドゥスを乗せた船はオランダ沿岸に近づいた時、突然の嵐に出会い、座礁してしまう。彼は何とか砂浜に泳ぎ着いたが、そこで意識を失う。数時間後一人のオランダ人漁師が彼を見つけて、自分の小屋まで連れていく。意識を取り戻した主人公は、ホルシュタインで習った低地ドイツ語の助けで、この漁師となんとか意思の疎通を図る。
漁師はゼバルドゥスがルター派の牧師であることを知って、アルクマールのルター派の説教師のところへ連れていく。同じルター派の聖職者との度重なる衝突や身の不幸のために、かなりの程度ひねくれていた主人公はこの人物に対しても初めは挑戦的な態度をとっていたが、善意の説教師に説得されて、その家に数週間泊めてもらうことになる。
こうして数週間が過ぎた時、一人の商人がロッテルダムからやってきたが、主人公はこの人物の次男の教育の面倒を見るという約束で、一緒にロッテルダムへ向かう。実はこの商人は、妻との結婚契約によって、最初の子は改革派の、そして二番目の子はルター派の教育を受けさせることにしていたのだ。かくして次男は主人公に預けられたが、それまで長男と次男の両方の面倒を見ていた改革派の家庭教師は、次男を自分の所有物のように見なしていたため、新しい家庭教師の登場には、不審の念を抱くことになった。
ここでニコライは、オランダにおける宗教状況について詳しく説明している。そして商人、その妻、改革派の家庭教師そしてルター派の家庭教師となった主人公の四人それぞれの宗派上の見解と立場の違いなどについて、具体的に叙述している。そしてこれらの人々の議論は、やはり神学論争となって妥協の許されない状況となっていった。その結果ゼバルドゥスは、数多くの宗派が共存している自由の土地アムステルダムへ移ることとなる。
商人からの紹介状を携えて意気揚々と主人公は朝の5時にユトレヒト門にたどり着いた。そこへ一人のドイツ人が現れ、手ごろな宿泊所へ連れて行ってやると申し出る。言葉が不自由で不安な思いに駆られていたゼバルドゥスにとっては、この同胞の出現はありがたい思いであった。そのため言われるままにこの男について行き、とある家の中に入った。その地下牢の中にはおよそ三十人ほどの哀れな人々が、わらの上に横たわっていた。

挿絵(アムステルダムの地下牢)
この光景を見た主人公は男に抗議したが、その答えとしてこん棒で殴られ、わらの上に倒れてしまった。実はこのドイツ人は植民地行きの兵士や船員を募集する一種の奴隷商人だったのだ。未経験な外国人とりわけドイツ人をだまして、家の中に連れ込み、東インドへと売り飛ばすのを仕事にしていたのだ。この後豚小屋のような地下牢の悲惨な有様が具体的に描写される。主人公はこの地下牢に数日間過ごした後、彼を含めて数人が、外の空気を吸うために、監視付きで戸外へ出ることを許される。そしてその帰途、運よく以前世話になったアルクマールの説教師に出会い、この聖職者が金を払ってゼバルドゥスは奴隷商人の手から解放される。
そのあと主人公はロッテルダムの商人から預かっていた紹介状を持って、一人の裕福な人物を訪ねた。この人物は幅広い学識と高潔な志の持ち主で、さまざまな貴重な著作を、自分の費用で印刷させていた。彼は主人公をことのほか信頼して、やがてその方面の仕事を主人公に任せるようになった。ところがこの誠実な男は、しだいに体が衰えていって、数か月後に死んでしまった。ただ亡くなる前にその全ての作品の残部と版権を主人公に遺贈した。
ゼバルドゥスはその後、冬の夜長を若い時から親しんできたイギリスの本を読んで過ごした。そしてその中の一冊を翻訳して、亡くなった人物の全作品の販売を行ってきた書籍商の所へ出向いた。このイギリスの書物は宗教的にかなり大胆な内容を含むものであった。はじめ書籍商はこの本の出版に乗り気であったが、知り合いの改革派の説教師がこの本を見て、危険な内容を含んでいる旨伝えたために、結局この本の出版はご破算になってしまった。
せっかく高揚していた気持ちに冷水を浴びせられて、落胆した主人公は、もはやその土地にいることがつらくなった。そこで結局版権代として百グルデンをもらって、ドイツとの国境に近いアーネム行きの郵便馬車に乗って、アムステルダムを離れた。ところが途中高熱が出て、馬車から降り、最寄りの土地で病気療養せざるを得なくなった。彼の病気は重篤で、旅費と宿泊代と医者の費用で、所持金の大半を使い果たしてしまった。ここで第七章は終わる。
次の第八章では、新鮮な空気と穏やかな日の光のおかげで、主人公の健康は回復する。そして滞在先の家の道路に面した生垣のところに出て、道行く人々からわずかばかりの喜捨をもらって生活するようになった。そしてある日彼は馬に乗った二人の人物を見た。例のゾイクリングとその家庭教師のランボルトの二人であった。世にも哀れな姿で生垣にたたずんでいたゼバルドゥスの姿を見かけたゾイクリングは、馬のうえから憐みの表情をうかべ、老人の手に一グルデンを握らせた。老人のお礼の言葉を聞きながら、馬を走らせる青年の目には涙が浮かんでいた。マリアンネと突然引き裂かれた後、この感傷的な青年は父親の家で過ごしていたのだ。彼は家に帰ってからも哀れな老人のことが忘れられず、翌朝再び同じ場所に行き、老人に頼んで身の上話を聞いた。そしてゼバルドゥスを父親の家に連れてきた。こうして主人公はゾイクリングの父親の家の居候となった。
この家の主人は戦争の際、軍隊への物資補給で思わぬ利益を得た。そして戦争が終わりそうになった時、ある騎士領を購入して邸宅を建てた。そしていろいろな美術品で邸宅内を飾り、有閑人としての暮らしをするようになっていたのだ。ゼバルドゥスとはほぼ同じ年齢だったこともあり、彼を話し相手として格好の人物とみなした。そこで主人公に住まいを与えたうえ、年俸まで支給した。主人公がやるべき仕事といえば、朝食の際に彼のためにあらゆる新聞を朗読することぐらいだった。そうした新聞には、この家の主人の好きな数字合わせのロッテリー(宝くじ)も載っていた。
いっぽう父親と再会したのもつかの間、再び離れ離れになった娘のマリアンネは、その後村から村へと渡り歩き、ある嵐の日に森の中の一軒の農家に身を寄せることになった。そして居候ながら安定した日々を過ごすようになっていた。その頃彼女はゾイクリング宛に自分の現在の身の上を手紙に書いた。ところがその手紙を家庭教師のランボルトが盗み読みして、ひそかにマリアンネに会って、ゾイクリングは死んだと嘘をついて、彼女の心を自分の方に向かわせようとした。
その間ゾイクリングの方は、父とゲルトゥルーティン夫人が引き合わせた彼女の娘アナスターシアと、しばしば言葉を交わすようになる。アナスターシアは彼の気持ちを自分の方に引き付けるために、いろいろと手を尽くすが、彼の方は動かない。そんな時彼は偶然、森の中でマリアンネに再会し、互いに今でも気持ちが変わらないことを確認して、指輪を交換する。そこへランボルトが現れ、怒りのあまりゾイクリングを襲うが、その場にいた農民によって撃退される。
最後の第九章では、その翌朝ゾイクリングの父親は息子を呼び寄せ、アナスターシア嬢を花嫁に迎えるよう提案する。しかし息子の方は森の中で、以前から愛していた娘に再会したことを告げる。それを聞いて父親は狼狽したが、息子の指の指輪に気が付く。そこに居合わせたゼバルドゥスは、その指輪から相手が自分の娘であることを知る。そしてゾイクリングに案内してもらって、森の中の小屋へと急ぎ、マリアンネに出会う。その後一同、ゾイクリングの父親の家に戻り、マリアンネを紹介する。そして父親の了解を得ようとするが、拒絶される。
その時ゼバルドゥスは、この父親の弱点を思い出した。そしてちょうど新聞に掲載されていた宝くじで自分は、一万五千ターラーの賞金が当たったことを告げる。花嫁の父親となる人のこの幸運にゾイクリングの父親の気持ちはなごみ、結婚は許可される。そしてさらにその場にランボルトが現れ、実は自分は長いこと消息を絶っていたゼバルドゥスの息子で、マリアンネの兄であることを告げる。
こうして物語は、最後になってすべてハッピーエンドとなる。宝くじの賞金は支払われ、ゾイクリングはマリアンネと結ばれた。また金持ちになったゼバルドゥス・ノートアンカーは義理の息子であるゾイクリングの隣人から小さな土地を買って、そこで幸せな老後の生活を送ることになった。
この小説への反応
以上の筋書きでお分かりいただけたかと思うが、娯楽人気小説の要素をふんだんに取り入れたものであったため、その人気の点では、ほぼ同時期に発表されたゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』をはるかに凌駕していたという。ニコライのこの小説は、なんといってもその神学上のテーマ(問題性)によって、人々をもっとも刺激したのであった。実際ニコライは、この成功によってその啓蒙思想を人々に伝える可能性が生まれた、と当時は思っていたようだ。そのため彼に反対する立場の人々は、「迷信の神の代わりに真実の神を置こうとする」彼の試みに、強く反発した。
ニコライは当時、キリスト教の存在、あるいは西欧の文化そのものが存続できるのか、それとも没落してしまうのか、という瀬戸際の認識を抱いていたようだ。そのため彼は真実のキリスト教を知らせることによって、迫りくる不可知論を撃退しようとしたのだ。それにもかかわらず彼に反対する立場の人々は、その真意を理解しようとはせず、彼のことを無神論者であると非難したのだ。
その一方、のちにニコライと対立するようになったゲーテやヘルダーといった作家は、この時はこの小説を少なくとも成功した「時代のドキュメント」として、受け入れたのであった。同じくのちにニコライと激しく対立した哲学者のフィヒテでさえ、「この本は時代の精神と傾向を十分反映したものである」としたのだ。
つまりこの時反対派の中心を形成したのは、同じプロテスタント信仰ながら過激な考えや行動が見られたため、小説の中でこっぴどくやっつけられた敬虔主義者やルター派正統主義者たちなのであった。彼らを代表する敬虔主義者ユング=シュティリングは、「『ゼバルドゥス・ノートアンカー』の著者たる軽蔑すべき俗物に対する牧童の投石器」という一書をものした。この書は、小説の第二巻が出る前の1775年に世に現れた。その前書きには次のように書かれている。「『ゼバルドゥス・ノートアンカー』の著者氏ならびにその塩見のきいていない殴り書きを嘲笑している人々の双方に対して、はっきりとこういわざるを得ない。つまり彼は宗教に対する厚顔無恥な嘲笑者であり、同時にへたくそな小説書きであると」。そしてその本文で、ニコライはプロテスタント教会の教えを笑いものにしたと非難し、宗教界の利益のために、説教者身分に対する嘲笑を嘆いている。
しかしこのユング=シュティリングは、本来ニコライが攻撃した論点には、十分説得力ある反論をすることができなかった。ニコライはもともと反動的な人々によってキリスト教が浅薄になていることに反対して声をあげたのだが、まさにその批判を通じて多くの同時代人の代弁をしたわけである。当時人々は漠然と教会のヒエラルヒーの硬直化を、悲しむべき退行現象だとみていた。そしてそれこそ真のキリスト教精神に永続的な障害をもたらすに違いない、と考えていたのだ。人々はまた、心の内面では次第に拒絶するようになっていた封建的社会秩序を管理面で支えていたのが教会である、とも次第に思うようになっていたわけである。まさにニコライはその『ゼバルドゥス・ノートアンカー』において、市民階級の自立解放を謳っていたために、この小説は多くの読者から歓迎されたのである。彼の封建制批判は、まさに正鵠を得たものと言える。
ところがこうした点には関心を持たずに、もっぱら哲学思想、文学、形而上学など、人間の心や魂など内面の問題に、その関心を集中させていた当時の思想家や文学者のなかには、この小説ないしニコライの立場に反発する者も出てきた。例えば北方の魔術師と呼ばれていたハーマンは、その『カドマンバールの魔女』と題した小冊子の中で、「ニコライは正統主義のドグマとなんら異なることのない合理主義のドグマに陥っている」と批判した。
これに対してニコライはハーマンと何度も文通したのちに、『ドイツ百科叢書』の第二十四巻の中で、ハーマンの著作の総合書評という形で反論した。そしてその中で彼の曖昧で不明瞭な文章を容赦なく批判し、分析している。これによってニコライは大家ハーマンと決定的に断絶することとなった。遠くケーニヒスベルクの地で執筆活動をしていたハーマンは、ニコライに言わせれば、文学界全般を見渡せる都会性というものを持ち合わしていない田舎者なのだ。そしてその作家活動を、社会全般への責任感なしに、ある種の近親交配の中で、自己満足に浸って行っている、ということになる。
しかしこの小説の出現の後、ニコライに反発して、たもとを分かった、かつての協力者もいた。それまでニコライは主としてその『ドイツ百科叢書』の書評者として多くの学識者を探し求めて、協力を依頼していた。しかしこの小説が出た後、例えば作家のヘルダーは書評誌への協力を断っている。またかつてその観相学研究に対してニコライが常に強い関心を抱き、文通をつづけてきたラーヴァーターは、これ以後二人の道は別であると認識して別れていった。さらに小説の中で兄弟のことをこっぴどく暴かれたと思った哲学者のF・H・ヤコービは、やがてこの攻撃的な小説家ニコライに対して結束するグループを結成した。そしてその陣営に、グライム、ヴィーラント、ゲーテなどを引き込むことに成功したのである。
こうして『ゼバルドゥス・ノートアンカー』の出現以降、ニコライを中心としたベルリン啓蒙主義の陣営と、あらたな敵陣営との戦線の位置が明瞭になったわけである。
