1 啓蒙主義と歴史研究
従来の見解とそれへの反論
「歴史は啓蒙の先頭に立って松明を掲げて進む」
ニコライはその晩年に当たる1806年に、こう書いている。ドイツにおいては、十九世紀から二十世紀前半にかけて、「啓蒙主義は非歴史的である」といわれ続けてきた。これは十九世紀初頭のロマン主義やランケを開祖とする歴史学派などによって広められてきた見解であるが、その影響力は強く後を引き、現代の歴史家ホルスト・メラーによれば、今なお多くの歴史学ハンドブックや一般の個別論文の中に、この見解は残っているという。
しかし歴史哲学者E・トレルチュは十九世紀末に発表した論文「啓蒙主義」の中で、十八世紀や十九世紀のフランスやイギリスと並んでドイツにおいても、歴史研究や歴史叙述が行われていたことを明らかにしている。そこではとりわけゲッティンゲン学派のガッテラー、シュレーツァー、ヘーレン、マイナース、ミヒァーエーリス、シュビットラーなどの名前があげられている。そして十七世紀の自然法学者プーフェンドルフによって歴史が神学から解放された後を受けて、彼らは新しい理念を歴史資料に適用していった、と述べている。
そして「もし啓蒙主義を非歴史的だと呼ぶとするならば、それは啓蒙主義が歴史をそれ自体ではなくて、それに基づいて行う立証や攻撃の手段として、あるいは政治的・道徳的教訓のために研究していたという、ただそのためだけからだと言えよう。この意味において歴史研究は著しい影響力を周囲に及ぼしてきたのだ。啓蒙主義は・・・それまで知られていなかったか、注目されていなかった世界を発見し、歴史の予測できない時代を切り開き・・・」と、トレルチュは続けているのだ。
続いて二十世紀前半には、メラーによれば、三人の歴史家ないし思想家「ディルタイ、マイネッケ、カッシーラーその他の偉大な人物による理念的解釈を通じて、十八世紀に目覚めた歴史的意識は新たなる再評価を体験した。それにもかかわらずとりわけ啓蒙主義にたいしてはなお<非歴史的>という厳しい裁断が下され続けた」という。
しかし現代の歴史家ヴァイグルはその『啓蒙の都市周遊』の中で、トレルチュがあげたゲッティンゲン学派のことをディルタイが高く評価していたとして、次のように述べているのだ。{それゆえにヴィルヘルム・ディルタイは、イギリスの啓蒙主義に連なることによって人間と世界を歴史的に見ることに寄与したゲッティンゲン学派の功績を強調して以下のように書いている。<十八世紀後半を通じてゲッティンゲン学派の人々から、歴史的学問にとっておおきな影響力を持った、相互に連関した一連の研究が生まれている。イギリス及びフランスの啓蒙主義の仕事がここで、ドイツの大学の研究活動が持つ学問的でまとまりのある体系的なやり方で、推し進められたのであった>。またヴァイグルは同書で「歴史的思考なるものは、ロマン派の世代が発見したというように記述されることが多いが、実際にはロマン派の世代がゲッティンゲン学派の啓蒙主義から学んだものなのである」とも書いている。
啓蒙主義と歴史との強い結びつきについては、現代の歴史家ユルゲン・コッカも、その『歴史と啓蒙』という書物の中で強調している。そこでは冒頭に掲げたニコライの言葉を引用した後、次のように述べられている。「我々の多くが歴史のプロ・ゼミナールで学んだかもしれないものとは逆に、いっぽうでは歴史は多くの(すべてのではないが)啓蒙思想家にとって中心的意義を持っている。・・・歴史学は、十九世紀の歴史主義の所産にすぎないといったものではなく、啓蒙とりわけ後期啓蒙の所産なのである。歴史学の創設者を探す際には、クラデニウスやガッテラー、シュレーツァー、イグナーツ・シュミットのような歴史家たち、ヴィーコやヘルダーのような思想家たち、メーザーやニコライのような実際家たち、ギボン、ヴォルテールあるいはファーガソンといった西欧からの影響を見落としてはならない。近年の史学史研究がそのことをあきらかにしている」
ニコライと歴史研究のつながりについて
ユルゲン・コッカはさらにニコライと歴史研究とのつながりについて、次のように述べている。「人は、社会の理性的な進歩を人類史的な尺度で期待しただけではなく、まさしくそれらすべてを通じて促進しようと欲したのである。すでにライプニッツとダランベールまたはニコライとメーザーは、有益で現在にかかわりを持つ、すぐれて批判的な歴史学を要求したのだ。・・・人は現代への歴史の批判的なかかわりを要求したが、現代のために歴史を手段化し歪曲することを求めはしなかった。そして歴史学について、社会-文明史という意味での極めて広い概念が抱かれていた。・・・後年に歴史主義が試みたような政治史への矮小化とは、啓蒙期の歴史はいまだ遠く離れていた」
以上利用してきたコッカやヴァイグルあるいはメラーの著作は、1970年代から1990年代にかけて刊行されたものであるが、ドイツ啓蒙主義に対する再評価の動きは、1960年代から西ドイツや西欧の研究者の間で見られるようになった「ドイツ十八世紀史見直し」の中で、全般的に行われてきたものである。ドイツの文学史や一般の歴史概説書の中ではなお啓蒙主義を非歴史的なものとする見解や叙述がみられるものの、すでに専門の歴史学者の間では「歴史と啓蒙」の深いつながりについては、常識化してきたといえよう。
このような流れの中で、従来ほとんど顧みられることのなかった歴史研究者としてのニコライの業績についても、研究する動きが出てきたわけである。そのなかでもドイツの歴史学者ホルスト・メラーは、この点について最も詳しい研究を遺している。この人物は1974年刊行の大著『プロイセンの啓蒙主義、出版者、ジャーナリスト、歴史叙述者フリードリヒ・ニコライ』のなかで、620頁のうち200頁を「啓蒙と歴史」の項目に費やしている。そしてさらに1983年には、そのダイジェスト的な単独の論文「歴史家としてのフリードリヒ・ニコライ」を発表している。私としては、このメラーの著作によって、ニコライの歴史研究者としての側面を知ったわけである。
以下の叙述では、ニコライが遺した歴史叙述に関する業績に基づいて、「歴史研究者としてのニコライ」について、さまざまな側面から考察していくことにする。
2 ニコライの歴史関連著作
ニコライが遺した作品を見渡すと、そのほとんどすべての著作の中に、歴史的テーマに対する所見や、歴史に対する際立った関心をうかがわせるような、ささやかな研究がみられる。そして啓蒙的思考の奥深くに歴史が定着していることについて、そうした所見や研究のなかでいろいろな言明が行われているのだ。これらの研究は、時間的にはまず地誌的な研究と重なった形で行われている。それは1770年代後半に始まり、1780年代、1790年代と続けられ、晩年の1806年の著作をもって終了している。
これらの歴史関連著作を内容別に分類すると、大きく四つの分野に分けられよう。
① ベルリン・ブランデンブルクの歴史的地誌
ー『王都ベルリン及びポツダム並びにそこにあるすべての珍しい事物についての
叙述』第二版(1779)、第三版(1786)の中の序章「ベルリンの
歴史」
② フリードリヒ大王に関する研究
ー『プロイセン国王フリードリヒ二世およびその周辺の人物に関する逸話並び
にすでに公刊されている逸話の訂正』(1788)
ー 『フリードリヒ大王に関するツィンマーマン氏の断編についての率直な所
見』(1791-92)
③ テンプル騎士団、薔薇十字団およびフリーメーソンに関する研究
ー 『テンプル騎士団に対してなされた弾劾並びにその秘密に関する試論。フ
リーメーソンの成立についての付論を添えて』(1782)
ー 『薔薇十字団及びフリーメーソンの起源と歴史に関するいくつかの所見。
このテーマに関する宮廷顧問官ブーレ氏の。いわゆる歴史的・批判的研究
に触発されて』(1806)
④ 文化史上及び言語史上の著作
ー 『古代及び現代における鬘(かつら)の使用について。一つの歴史的研究
』(1801)
次に以上の歴史関連著作の概要を、順次見ていくことにしよう。
(1)ベルリン・ブランデンブルクの歴史的地誌
『王都ベリリン及びポツダムについての叙述』の第二版
序章「ベルリンの歴史」
ニコライの歴史研究の初期段階にあっては、地誌的な研究を補完するような形で進められた。それは初版の序章として書かれた、ベルリン地域の淵源からニコライの時代までの歴史に関するごく短い素描であった。その後広範で徹底的な史料研究に乗り出し、十年後の1779年に内容的に全面的に書き換えて、第二版を刊行した。
社会・経済史的叙述
ここでは十二世紀におけるベルリン入植からニコライの時代までの発展の歴史が、様々な史料や文献に基づいて詳細に跡付けされている。ベルリン入植は西部ドイツ地域の人々による東方植民の一環として行われたものであるが、その後の移住の発展とそれに結びついたブランデンブルク・プロイセンの経済的興隆の様子が、詳しく叙述されている。それは政治・外交史的なものではなくて、「社会・経済史」的なものであった。
そこで彼はキリスト教会が実施し、保管していた住民の婚姻・誕生・死亡に関する諸記録など統計的記録を主たる史料として用いた。そして歴代の君主による重商主義的「植民政策」を肯定的に評価している。その際ニコライは、教会記録簿に基づいて一般的な人口発展のモデルを作り出した、ベルリンの牧師で統計学者のジュースミルヒの手法を用いたのだ。しかしニコライはそれぞれの歴史的背景との関連でこうした統計データを分析できるようにするために、たとえば人口数を戦争、疫病、凶作、物価高騰などと結びつけて、歴史事象の因果関係を説明している。
またニコライは史料を入手するにあたって、その豊富な人的ネットワークを利用することができた。その間の事情について彼は次のように説明している。
「その後の十年間に私はわが町の歴史や現状についての知識を深めるために、努力を重ねてきた。その際ヘルツベルク大臣閣下のご厚意により、王立文書館を使用する許可が得られた。さらにあらゆる身分の愛国者の方々が、ベルリンに関する様々なことどもについて、熱心に情報をお寄せくださった。かくして私は、1779年に二巻の新しい版を刊行することができたのである」
史料収集と編纂の仕事
ニコライの歴史に対する強い関心は、やがてまたベルリン地誌との関連でべつの発展をみせた。それは十七世紀の大選帝侯以後の「芸術家・職人一覧」を独立した書物として刊行させたのである。それは歴史叙述というよりは、史料の収集と編纂の仕事であったが、それらは現在なお史料的価値を有するものがすくなくない。史料収集の苦労についてニコライは次のように書いている。{それらの情報を私は、王立文書館史料、ベルリン所在の様々な教会の記録簿、市民の古い記録簿、その他の手書き及び印刷の史料を通じて集め、さらに部分的には自ら芸術作品を見に行くことによって収集したのであった」
ニコライの「ベルリンの歴史」は、可能な限り多くの史料を方法論的に正確に使用し、その基盤の上に立って、一つの時代の生活全般を広範にとらえようとした点に、特徴があった。その意味でこの作品は「十八世紀の模範的な地域史の一つに数えられるばかりでなく、ドイツの歴史叙述上の画期的な業績の一つにも数えられる」と、現代の歴史家メラーは高く評価しているのだ。そしてそうした十八世紀の地域史の傑作として、そのほかニコライの友人メーザーが書いた『オスナブリュック史』及びゲッティンゲン学派のシュピットラーによって著された『ハノーファー侯国史』を挙げている。
(2)フリードリヒ大王に関する研究
これに関連してニコライは1788年から1792年にかけて、前述した二冊の著作つまり『プロイセン国王フリードリヒ二世及びその周辺の人物に関する逸話並びにすでに公刊されている逸話の訂正』(以下『フリードリヒ大王に関する逸話』と省略)、及び『フリードリヒ大王に関するツィンマーマン氏の断編についての率直な所見』(以下『ツィンマーマン氏の断編についての所見』と省略)を公刊した。この二つの著作は互いに緊密な関連を持ったものであるが、まず『フリードリヒ大王に関する逸話』の方から、取り上げていくことにする。
A 『フリードリヒ大王に関する逸話』
本作品の成立の経緯
こらは1788年3月にまず第一分冊が刊行されてから順次発行が続けられ、1792年3月の第六分冊をもって完了している。この著作はフリードリヒ大王(1712-1786)に関する逸話をニコライ自身が収集した部分と、それ以前に出回っていた逸話を訂正した部分とからなっている。その成立の経緯については、ニコライが第一分冊の前書きに書いているところから、明らかである。
それによると1787年7月ニコライが転地療養のために滞在していたヴェーザー川流域の保養地ピュルモントで、滞在客がそろってフリードリヒ大王ゆかりのケーニヒスベルゲへ出かけた時、人々がめいめいその前年に亡くなった大王をしのんで、様々な逸話を披露したという。それ以前から大王に強い関心を抱いていたニコライは、そうした逸話の多くが間違ったものであることに気づき、それらを訂正していった。それを聞いていたニコライの長年の友人で宮廷顧問官のツィンマーマン氏は、大王についての逸話をまとめ、あわせて世に出ている間違った逸話を訂正して一冊の書物にしたらどうかと、ニコライに提案したという。その時ニコライは時間的な余裕がなかったためあきらめていた。しかしその時の提案はいつまでも彼の脳裏に焼き付き、やがて多忙な出版社の仕事の合間を盗んで、それを実行することにしたのであった。
ニコライの大王への敬愛の念
ベルリンに生まれ育ったニコライは、若い時からこの大王を敬愛して、その行為や性格に強い関心を抱いていたという。「フリードリヒ大王が統治していた時代は、わが青春の幸せな歳月であり、また熟年の黄金時代でもあった。私が精神の陶冶と世界認識に関して身に着けたいと思っていたことを、私はこの時代に、大王の率直で偏見のない思考法の影響の下で獲得したのである」。このように「前書き」の中で青春を振り返り、国王による思想の自由の保証をニコライは称揚したのであった。そして本文の中では、七年戦争(1756-63)および戦後の時代の苦しい状況の下で大王が成し遂げたことどもを、社会経済的な側面を含めて記述しているのだ。
その際彼は、そうした大王の統治の偉大な実績が世にほとんど知られていないことを嘆いている。つまり世の多くの人々は大王のことを戦争に強い、単なる軍人だと思っているというのだ。しかし注意深く観察していたニコライにとっては、大王は戦時における軍事的才能や英雄的な勇気と並んで、平和時には国家の繁栄と人々の福祉の増大に尽力を惜しまない善行の人だったのだ。さらに人間味があり、ユーモアを解する人物で、フルートを吹き、作曲もする文化人であり、さまざまな著作をものする哲人ないし思想家でもあったのだ。
逸話の出所の吟味~史料批判の厳しさ~
ところでニコライは逸話の真実性を高めるために、その出所を慎重に吟味した。つまり史料批判にも彼は厳しかったのだ。その際彼は、国王の周辺に長いこといて、国王のことをとてもよく知っていた三人の男と親しくしていたことを、明らかにしている。その三人とは、音楽家のクヴァンツ、ダルジャン侯爵そしてイツィリウス大佐であった。「前書き」の中で三人のことが。次のように書かれている。「クヴァンツは1734年に国王の面識を得て、1740年以降(戦時を除いて)毎日二~三時間国王の部屋にいた。・・・この老人から私はとても注意深く話を聞き、いろいろ質問し、それにたいして非常に詳しい回答をえていた。・・・国王の音楽にまつわる逸話をクヴァンツ及びその音楽仲間からとても詳しく聞いていたが、それらはハンブルク在住のエマヌエル・バッハを除いて、おそらく現存する誰からの話より詳しいといえるだろう。ダルジャン侯爵はその治世の初めから国王の話相手で、王の信頼の厚い人物であった。イツィリウス大佐はちょうど七年戦争の危機の時期に王の周りにいたが、戦争によってひっ迫した財政を立て直そうという時でもあり、当時進行中の諸計画に彼は参画していた。・・・この三人から私は、国王の本当の性格について多くの事例との関連の中で、光を与えてくれた実に様々なことを聞いたのである」。
この三人以外からもニコライは多くの人々にいろいろ尋ね、さらに関連した書物や手書きメモや文書に当たって、ちょっとした逸話でもそれが真実であるかどうか検証に努め、叙述に際してはその出典を明示している。彼の「真実への愛好癖」は、それ以前に世に出回っていた逸話を放置しておくことができず、それらをできる限りの範囲で取り上げ、間違った個所を指摘し訂正しているわけである。
逸話の概要

『フリードリヒ大王に関する逸話』への挿絵(コドヴィエツキー作)
こうした逸話の中身を見ていくことにしよう。ニコライが集めた逸話の数は94に及び、訂正した逸話は29に達している。彼が収集した逸話は多岐にわたっているが、あえてそれらを分類してみると、おおむね次のようになろう。
イ 七年戦争中の大王の生活を示すもの。陣営でのエピソードなど。
「ロイテンの戦いの勝利の後、国王が陥った二重の危機」、「行軍中の兵士た
ちが疲れた時に行われた国王の演説」、「ナッサウ竜騎兵隊創設に関する
国王の勅令」、「国王がライプツィヒの陣営で犬に餌をあげているときの
ダルジャン侯爵との会見」
ロ 国王の民衆に対する公正さ、やさしさを示すもの
「農場経営の失敗により追放された入植者を、国王が呼び戻した話」、「ある
貴族の夫人が、借金返済の件で国王に裁きを願い出た話」、「食器を壊した
り、客にスープをかけてしまった召使への優しい思いやり」など。
ハ 国王の統治に関するもの
「学校教育に関して自ら出した勅令」、「ハレの孤児院や教育施設の視察」
「裁判の短縮及び迅速化についての大臣との会話」、「イギリス艦隊を巡っ
ての部下との議論」など。
ニ 国王の知性・学識並びにユーモア・機知を示すもの
「教父の全作品についての国王の冗談半分の思い付き」、「国王は地上における
神の似姿であるとの考えについての、国王の愉快な思い付き」、「神聖ローマ
帝国に存在する三つの宗教に関する国王の見解」、「国王自筆の、様々な欄外
の書き込み」、「国王、無限小や微分計算について尋ねる」、「(ローマの)
トラヤーヌス帝と大王の手紙の類似性」など。
ホ 著名人との交際
「哲学と宗教についてのズルツァーとの対話」、「モーゼス・メンデルスゾー
ン、国王からポツダムへ招請される」、「ゴットシェート教授との対話」、
「イギリス公使との対話」
ヘ 国王周辺の人々について
「ダルジャン侯爵ほか数人の国王の話相手の横顔」、「ブラウンシュヴァイク
公爵未亡人にあてた国王の手紙」、「ダルジャン侯爵のフランスへの旅とそ
れに続く彼の死」、「イツィリウス大佐の人間模様」、「クヴァンツ、国王
に仕えることになる」
ト サン・スーシー宮殿を巡る話
「国王、新宮殿内に天井画を描かせる」、「庭師、庭園内の大理石彫刻の苔を
はがそうとする」、「宮殿内の小さな城壁の修理」、「サン・スーシー新宮
殿の造営について」
チ 国王の乗馬について
「国王の乗馬法、乗馬の数、馬の調教の仕方」、「自分の馬に名前をつける時
の国王の癖」、「国王、何度も馬もろともに倒れる」、「怠け者の白馬」、
「普段着の国王が乗るコサック馬」、「戦争中に国王の馬が受けた災難」など
リ 音楽をめぐる話
「国王のフルート演奏」、「国王の作曲」、「フルート演奏の際に見られる
国王とクヴァンツとの意見の相違」、「プロイセン王国の最初の二人の国王
時代の音楽状況」など
ヌ 大王の皇太子時代の逸話
「皇太子として父王の前でフルート演奏して、驚かせる」、「1730年のフ
リードリの逃亡と逮捕に関する信頼できる情報」、「フリードリヒ、キュス
トリンの官署で事務官として執務」、「「キュストリンの官署の長、皇太子
のために便宜を図り、先王により解雇される」
B 『ツィンマーマン氏の断編についての所見』
本作品成立の経緯
これは前述の『大王の逸話』を順次刊行していた途中に、ニコライの長年の友人であったスイス人の著作家リッター・フォン・ツインマーマンが世に出した『フリードリヒ大王の生涯・統治・性格に関する断編』(1790)を読んで、その書評として自ら編集した書評誌『ドイツ百科叢書』に掲載したものを、その後独立した書物の形で刊行したものである。ツインマーマンはハノーファー侯国在住のイギリス王の宮廷顧問官兼侍医をつとめていたが、フリードリヒ大王の死の直前に、その相談相手になっていた。そして前述したように、ニコライに「逸話」を書くよう勧めた人物であった。この時の彼の意図がどのようなものか定かではないが、この伝記を刊行してからは、ニコライ及びその周辺の<ベルリン啓蒙派>の人々との仲は、悪くなってしまった。
ニコライの本著作がどのようにして生まれたのか、その経緯についてニコライは次のように述べている。「フリードリヒ大王に関するリッター・フォン・ツィンマーマン氏の断編は、刊行された時ドイツ人の間にセンセーションを巻き起こしました。この著者の著名さ、手に入れた素晴らしい諸史料、彼の他の書物にも見られた膨大な量の新しい情報は、当然のことながら世の注目を浴びたのです。そしてとりわけプロイセン王国以外に住む、少なからぬ読者は、今やこの断編こそは、フリードリヒ大王の生涯に解明の光を与えるもの、と信じたのです。しかしやがてよその国よりも多くの事情を知ることができ、十分検証しることができるプロイセン王国に住む多くの読者の間から、疑問の声が発せられようになりました。さらに『ノイエ・ドイチェ・ムゼウム』(1790)やビュッシング氏の著作の中でも、たくさんの間違いや矛盾が指摘されるようになりました。またベルリンの諸官庁の方々から、自分たちの部局に関係して、その人たちが最もよく知っている事柄について、少なからぬ誤りがみられるという指摘が私の手元に届きました。そして『ドイツ百科叢書』の書評の形で、それらを報告したいとの希望が伝えられました。そこで私としては感謝の念をもって、この申し出を受け入れたのです」
これでわかるよに、本作品はここで言及されている官吏のほか影響力のある政治家など多くの人々の所見を、ニコライが編集者としてまとめたものであったのだ。しかし本文の中では、「我々は」とか「編集者は」という表現が用いられて、所見を寄せた人の名前は記載されていない。そして作品の構成や史料の吟味・補完などはニコライ自身で行っている。
本作品の内容
本著作はツィンマーマン氏の三巻に昇る作品について、「第一章 断編の概観、目的及び史料について」から始まって、「第三十二章 フリードリヒ大王の、なお十分には解明されていない側面・・・について」に至るまで、原文の章立てに即して、一つ一つ大変詳しい批評と所見を掲載している。そして第一部、第二部合わせて321頁にも及び、巻末には人名索引までついている。つまりこの作品は通常の意味での書評の枠をはるかに超えて、ニコライ自身の歴史観や歴史方法論まで織り込んだフリードリヒ大王時代のブランデンブルク・プロイセンの歴史研究となっているのだ。
ニコライはまず、「第一章 断編の概観、目的及び資料について」の個所で、ツィンマーマンの原文の四~五ページから次のように引用している。「民間伝承によるでもなく、ベルリンの酒場に取材したものでもなく、第一次史料から入手したことに基づいて、あのように偉大な対象について何か書くということは、全く他意のない試みなのである。・・・私はフリードリヒ大王の生涯からこの断編において、記憶すべき事柄を取り上げるが、それらの大部分は書物や外国の伝承に基づくものではない。それらはフリードリヒの手書きの手紙、彼の近くで彼とともに生活していた高貴な人々からのとても多くの手書きのメモ類、彼の事業への参画者からの口頭による情報、そして長年彼の話相手であった大臣に対する私の書簡による質問への回答などから成っている。これら全ての情報や事実を、私は人々がフリードリヒの驚くべき性格について、いささかなりとも誤解しないという、唯一の目的に向けて用いていく所存である」
この一次史料に基づいた叙述という姿勢そのものは素晴らしいものとして認めたニコライは、それにもかかわらずツィンマーマンの作品には、いたるところで時、名称、場所などを含めて、事実誤認や不正確な表現、一見して分かる誤りが多いと述べ、その理由ともいうべきことを次のように記している。{歴史に対して豊富な史料を見つけ出すことは、とても価値のあることだ。しかし史料を十分評価するためには、それにふさわしい知識と才能を持たねばならない。・・・史料だけでは、まだ歴史叙述者になれないのだ」。「彼自身の知識や判断力や厳密さの不足、たくましい想像力や過剰な感情移入そしておそらく彼のうぬぼれや気性の激しさなどが、素晴らしい史料を適切な形で用いることを妨げているのであろう」。
このようにツィンマーマンを批判する一方、ニコライは一般にフリードリヒ二世及びその時代について書こうとする歴史叙述者が満たさねばならない前提条件を次のように提示している。「フリードリヒ大王の生涯について書こうとする者は、まずすべてのヨーロッパ諸国の歴史と統計に関する知識を持たねばならない。とりわけその長い在位期間中に王が直接衝突した国々についての知識が重要である。・・・また商業、工業、マニュファクチャー、工場とかかわりがあると思われる事柄について、把握していなければならない」
この言葉から分かることだが、ニコライが目指した歴史叙述の在り方は、先に「ベルリンの歴史」で実行したような人口学的・統計学的な手法による社会経済史的な叙述であったのだ。
社会経済史関連でのニコライの見解披瀝
ニコライは続く第二章から第三十二章まで、ツィンマーマンの作品の誤りについて、彼の協力者の指摘を具体的に記すのと同時に、原作のテーマに即してそれらに対する自らの評価や所見を、かなり詳しく述べている。例えば第二章の父王フリードリヒ・ヴィルヘルム一世に関する箇所では、軍人王ないし兵隊王などと呼ばれ、とかく評判が悪かったこの国王に対して、ニコライは大変肯定的な評価を与えている。「国家行政における秩序と著しい節倹、個々に見られた有益な勤勉の促進、とりわけマニュファクチャーの奨励は、フリードリヒ・ヴィルヘルム一世の大きな功績であった」。この後ニコライは、この国王が家屋、教会、橋梁の建設を支援し、沼沢地帯の開墾を促進し、農業と王領地経営の改善を進め、とりわけプロイセン領リトアニアに再び入植を行ったことを、この国王のさらなる業績であった、と称賛しているのだ。
このようにニコライはツィンマーマンの原作に対する所見という形から出発しながら、書評の枠組みをはるかに超えて、社会経済史上の様々な領域に関して、自らの見解を披歴しているわけである。そこには国家の経済・社会政策の重要分野がほとんど網羅されている。そうしたニコライの研究成果は、フリードリヒ二世の歴史に関する第一級の歴史家ラインハルト・コーザーが言うように、あるいは最近の研究水準との比較が示すように、事実に即していて大変価値があるものなのだ。
その際上に述べた領邦君主は、当時一般的であったと思われる宮廷生活の価値基準ではなくて、労働と達成された業績という啓蒙化された市民身分の「職業倫理」によって、その価値が判断されたのであった。ニコライのような啓蒙市民は、聖職者や貴族あるいは教会や政治権力の干渉からすでに自由を獲得していた。そしてこうした観点から、フリードリヒ大王のような啓蒙専制君主は<国家第一の僕>となったわけである。この場合専制君主ではあっても、原則として批判可能な存在となり、君主はその業績によって評価されたのであった。
いっぽうニコライは、一国における経済的・文化的進歩は、単に君主の功績に属するものでない事も、強調した。それはニコライの歴史叙述の重点が、君主と戦争の歴史から、経済・社会・精神の歴史へと移っていたことにも示されていると言えよう。こうして歴史叙述の中に、君主だけではなくて、臣下(一般民衆)も登場してきたのである。この意味でニコライはずっと以前の1774年に、『ドイツ百科叢書』に「改革者ヴォルテール」と題する書評を掲載して、民衆の登場を強調しているのが注目されるのだ。
ヴォルテールにせよニコライにせよ、これらの著作家たちは宮廷歴史家ではなくて、彼ら自身の身分(市民身分)の業績を歴史の中に探し求めて、叙述したのであった。こうした関心領域の拡大は、歴史方法論の決定的進歩と手を携えるようにして行われたのであった。
(3)テンプル騎士団などに関する研究
A 「テンプル騎士団、薔薇十字団およびフリーメー
ソン研究」
本作品成立の経緯
本著作の正式な表題は『テンプル騎士団に対してなされた弾劾並びにその秘密に関する試論。フリーメーソンの成立についての付論を添えて』(1782)である。ニコライ自身その会員であったことがあり、のちに脱会したフリーメーソン協会の成立とテンプル騎士団との関連を探ろうとしたことが、本著作執筆の動機であったという。
ニコライの時代、フリーメーソンの起源としてテンプル騎士団の名前を挙げる書物もたくさんあり、そのことを口にする人も少なくなかったという。そうしたことが契機となってニコライは本書を書くことになったのであるが、その本論の部分で彼はテンプル騎士団の歴史を叙述したのではなく、十四世紀初頭に起きたその悲劇的結末にまつわる事情を研究したわけである。専門家によれば、約二百年に及んだ騎士団の歴史そのものよりも、異常な結末を迎えた同騎士団の最後に関する研究の方が盛んなのだそうであるが、ニコライもそれに倣ったものと思われる。というよりもむしろ強制的に廃絶された後の騎士団の運命や、地下で連綿と続けられてきたといわれる動きとフリーメーソンの成立との関連に、ニコライは強い関心を寄せて本書を執筆したようである。
ちなみに二十世紀イタリアの作家ウンベルト・エーコが書いた『フーコーの振り子』という作品は、私も読んだが、まさにテンプル騎士団のその後の運命にまつわるミステリー風の物語なのである。
本論に入る前にまずニコライとフリーメーソンとの関係について、簡単に触れておきたい。プロテスタント正統主義の立場に立っていたニコライは、1781年に行った南ドイツ及びオーストリア地域への大旅行の際に、カトリック教会というものに初めて肌で感じるほど生々しい形で接触した。以前からカトリックに批判的であったニコライは、この時以来その神学上のカトリック批判を強め、とりわけ戦闘的なイエズス会にその批判の矛先を向けるようになった。イエズス会は1773年にローマ教皇クレメンス四世によって廃止に追い込まれたが、ニコライの見解によれば、その廃止以後一般社会から身を隠しながらも、秘密のヴェールに包まれた部分の多かったフリーメーソン協会にひそかに潜入して、そこに広まっていた秘密儀式に携わるようになっていた、というのだ。
ニコライが所属していたのは、ベルリンにあった「三つの地球儀」というロッジであった。当時ヨーロッパ中に広まっていたフリーメーソン協会は、ロッジと呼ばれる支部によってその実態はかなり異なっていたようだ。ニコライは自分が所属していたロッジでの経験から、この教会内部では厳密な会則に従った階層的な構造が支配していたことを明らかにしている。この高度位階制といわゆる「未知の上位者」への絶対的服従といった協会内部の秘密主義は、本来あるべき啓蒙主義の公開への要請という根本原理に反するものだ、というのがニコライの立場であった。彼の眼には、位階制や絶対服従は、公平な批判、真理の探究そして健全な理性の普及などを、妨げるものに見えたのだ。そして秘密保持のヴェールの陰に隠れて闇の力が結束して、啓蒙に戦いを挑んでいるようにも見えたのだ。
ところでフリーメーソンの起源を巡っては、古来様々なことが言われているが、1717年にロンドンに「思弁的」フリーメーソン団が誕生する以前には、いわゆる「実践的」フリーメーソン団として、数多くの中世的な同業・同職組合との関係が指摘されている。その一つに「フラン・メチエ」と呼ばれる同業信心会があったが、これの発生にあずかって力があったのが「テンプル騎士団」であったという。この騎士団は十字軍の時代の1118年に聖地防衛を目的としてエルサレムに設立された。そしてその周辺に城砦を作ったり、教会を建てたり、道路や橋梁の建設に従事したりした。
その間に彼らは東方の建築術をこととする諸集団と密接な関係を結んだ。そしてやがて習得した建築術を西方のヨーロッパへともたらした。こうしてヨーロッパのいたるところでテンプル騎士団は、ギルドや同職組合に入り込み、重要な役割を果たすようになった。そして石工(メーソン)、大工、モルタル職人などはほとんど全員、テンプル騎士団の領地に居を構えるようになった。「実践的」フリーメーソンの中核に「石工(メーソン)」の組合があったことは、一般的に認められている。この点にもフリーメーソンの起源としてテンプル騎士団の名前が出てくる所以があったと言えるのではなかろうか。
テンプル騎士団の悲劇的結末
西暦1307年10月、フランス在住のテンプル騎士団全員が逮捕されるという事件が発生した。推測と強い疑惑に基づいて行われたこの逮捕に続いて、命令を出したフランス王フィリップ四世の宣言文がパリで配布され、一般公衆に逮捕命令書に盛られた告発事項を知らせている。これらの告発事項は、テンプル騎士たちの背教、猥褻な典礼,男色、偶像崇拝などの罪状を連ねたものである。この告発に基づいて、テンプル騎士たちに対する異端審問官による尋問や教皇クレメンス五世による裁判などが行われる。そしてヴィエンヌ公会議が開かれ、1312年フィリップ四世の強い要請によって、テンプル騎士団の廃止とその財産をヨハネ騎士団に移すことが決定される。その際騎士団長ジャック・ド・モレー以下数人の幹部が火刑に処せられ、それ以前の拘留中に行われた拷問によって多数の騎士が命を落としている。
以上がテンプル騎士団の悲劇的な結末の概要であるが、こうした残虐な仕打ちは、十八世紀の啓蒙主義者にとっては、中世的な非人道的な行為の典型的な例とみなされた。たとえばトマジウスやヘルダーもこの問題に取り組み、非人道的な裁判を非難して、騎士団を弁護する論調を展開している。
啓蒙主義者ニコライも、本著作において騎士たちに科せられた数々の罪状を分析し、検討しているのだが、その際ニコライが取った態度は、批判・実証的な歴史研究者としての態度だった。つまりニコライは歴史研究に当たっては、啓蒙的道徳的判断を排除し、党派性や感情移入を拒否して、歴史認識の客観性を保とうとしたのであった。そのためにここでニコライが行った分析や叙述は、イデオロギー的・道徳的評価がもたらす影響への批判にもなっているのだ。
とはいえ啓蒙主義者ニコライにとっては、人道主義の絶対的要請というものも無視することはできなかった。そうした微妙なバランスの上に立って、彼はこの問題を論じていったのであった。
騎士団弾劾に対するニコライの所見
ニコライは本著作の第一部の前半で、騎士団員に向けられた非難・告発の一つ一つを取り上げて、子細に検討し適切な所見を述べている。そこでニコライは、極めて特殊なまさに骨董品的な、深く細部に立ち入った興味と関心を示している。この研究を通じてニコライは、カトリックの教義の歴史に対する驚くべき知識を披露してもいるのだ。
付論『フリーメーソンの起源』
第二部の後半でニコライは、本作品執筆への動機づけとなったフリーメーソンの起源についての研究を、付論の形で掲載している。当時フリーメーソンの上層部によって、フリーメーソンは廃絶されたテンプル騎士団と直接関係があった、という主張がなされていた。彼らは秘密主義と神話形成の力によって、自分たちの影響力を拡大するために、一つの伝説を作り上げようとしていたわけである。こうした動きに触発されて、ニコライもその起源を研究しようという気持ちになったのである。
この論文のはじめにニコライは、その少し前に亡くなった友人のレッシングが書いたフリーメーソン談話『エルンストとファルク』を取り上げている。そこでは暗号化された形ではあるが、「新しいテンプル騎士団員」が話題となっていたからである。ニコライによれば、その中でレッシングは、テンプル騎士団の組織はその後ずっと存続してきたが、その組織から十七世紀末に建築家クリストファー・レンによってフリーメーソン協会が創設されたと主張しているという。それに対してニコライは、テンプル騎士団の後継の秘密組織が何らかの重要な意図なしに、四百年間も存続してきたとは、自分にはとうてい考えられないとしている。
そして十七世紀のロンドンで何かが発見されたとするならば、それは古い組織を模範にして新たに創設されたものと考える方が、自然であるとしている。続けてニコライは自分で集めた史料を基に、十七世紀のイギリスに焦点を合わせた自己の研究成果を明らかにしている。そして建築家レンに先立ち、古典古代の研究者アシュモールがすでに1646年にフリーメーソン協会に加入していたと記述している。この人物はイギリス国王チャールズ二世の寵臣で、薔薇十字思想を非常に礼賛していた。そうした秘儀参入者たちが自然の秘密を探求し、霊的にソロモンの館を建築することを目的とする結社を、1646年にロンドンに組織したという。
テンプル騎士団とフリーメーソンをつなぐ薔薇十字団
ここからニコライはテンプル騎士団とフリーメーソンをつなぐ存在として、この薔薇十字思想ないし薔薇十字団というものに注目し、「フリーメーソンの起源を詳しく知るには、私としては別の、これもとても有名な薔薇十字団の起源を探る必要がある」と述べている。この後ニコライは、南西ドイツ、ヴュルテンベルク出身の神学生アンドレーエを薔薇十字思想の生みの親だとして、1616年に発表された彼の小説『1459年のクリスティアン・ローゼンクロイツの化学の結婚』に触れ、そこに現れた薔薇十字思想について詳しく解説している。
当時のドイツは、カトリックとプロテスタントの両勢力が激しく対立し、三十年戦争が勃発する前夜の状況にあった。このころ起きた薔薇十字団騒動については、実にたくさんの文書や史料が遺されていたが、ニコライは「アンドレーエの書いた著作及び薔薇十字文書の多くを読んだ。そして・・・私のようにしようとする者は、アンドレーエがこの協会を道徳的・政治的意図から、一つの詩(虚構)として考えたことを理解するに違いない。しかし彼の詩(虚構)は多くの同時代人によって真実として受け止められ、各人が自分流のやり方で解釈し、その結果一部に全くばかげた事態が発生したのであった」。全く真摯な情熱をもって教会を改革しようとして薔薇十字思想の普及を考えていた若き善良な神学者アンドレーエは、自分が著した著作が思いもかけぬ熱狂と反発を引き起こしたことにおどろいた。そして自分への迫害も痛切に感じたため、自分の計画を取り下げ、薔薇十字騒動から身を引いた。しかし一度世の中に広められたその思想は消えることはなく、様々な形で後世に影響を及ぼすことになったのである。
ニコライは薔薇十字思想の中核にパラケルススの思想や錬金術的ないし占星術的思考があったことに触れた後、この思想がやがてイギリスにわたって、当時の政治や宗教とのかかわりの中で、やがてフリーメーソンへとつながっていく道程を、先のアシュモールの役割や1660年の<ロイヤル・ソサエティ>(王立協会)の創立に絡めて詳述している。
ニコライはその後の薔薇十字思想の流れを、大きく四ないし五のグループに分けているが、イギリスへの影響の点で重要な人物として、ミヒァエル・マイヤーとロバート・フラッドの二人を挙げている。マイヤーはドイツ皇帝ルドルフの侍医で錬金術師であったが、その思想はアンドレーエのものとはかなり違っていて、神秘主義の装いをより強く持っていた。もう一人フラッドはロンドンの医者であったが、その思想はパラケルススの医学とグノーシスの哲学に自らの物理学的要素を加味したものであった、とニコライは述べている。
次にニコライは近代哲学の先覚者の一人であったフランシス・ベーコンを登場させている。そして自然科学の進歩に壮大な夢を託したユートピア物語『ニュー・アトランティス』のあらすじを紹介して、自然研究の場としてのソロモンの館に関する記述が当時、一般に大きな注目を浴びたことを指摘している。次いでこのベーコンの思想が薔薇十字の思想とまじりあって、十七世紀半ばのイギリスの内乱の時代に多くの知識人に強い影響を及ぼした、としている。当時のイギリスの知識人の多くは、革命や凄惨な戦乱の渦中にあって、神秘的でほとんどグノーシス的な哲学思想を胸に抱いていたという。占星術や呪術はなお人々の心を強くとらえていた。そうした情勢の中で当時唯一の実験的な科学であった化学も、こうした色彩に彩られていたのだ。
学者の教えや実験は、錬金術師の具象的な比喩をもって初めて当時の人々の理解が得られたという。薔薇十字思想の原典といわれるアンドレーエの『化学の結婚』も、錬金術に深くかかわっている。この事からも分かるように、自然科学研究という近代への第一歩は、なお薔薇十字思想に結集していた中世的な神秘主義的彩りを媒介して、初めて記されたわけである。
フリーメーソンへの歩み
こうして前述したアシュモールは、占星術師、医師、数学者、聖職者などを集めて、霊的にソロモンの館を建築することを目的とする結社をロンドンで組織したわけである。この後ニコライはこの知識人の組織がフリーメーソンへと発展していく経緯について、次のように述べている。「ロンドンで市民権を有する者はだれでも、何かのギルドに属していなければならないことは、周知の事実である。・・・この協会の何人かの会員は石工(メーソン)のギルドに属していた。このことによって彼らはその会合の場所として、石工のギルド会館(メーソンズ・ホール)を利用する機会を得た。そしてその他の会員も石工のギルドに加入し、<フリー・アンド・アクセプティッド・メーソン>と称し、石工ギルドのシンボルを用いた。ここではフリーという英語は、誰かがある協会またはギルドの会員としての権利を有している、という意味なのである。・・・アクセプティッドという言葉は、この特別の協会が石工ギルドによって受け入れられたことを意味しているのだ。このようにして後に有名になったフリーメーソンという言葉は、元来偶然生まれたものなのだ」
このようにしてフリーメーソンの、いわば原型が誕生したわけであるが、初期のうちはあくまでも石工職人ないし自然研究者の、とらわれのない会合の場であったことを、ニコライは強調している。しかし同時にこの団体に集まった人々は、政治的には、反議会の王党派であったため、クロムエルを中心とした清教徒・議会派と、チャールズ一世を中心とした王党派の間の政治的争乱に彼らも巻き込まれた経緯が、その後かなり詳しく叙述されている。しかし様々な紆余曲折を経て、1660年に王政復古がなり、チャールズ二世が即位するの及んで、この王党派の組織であるフリーメーソンから、自然研究を目的としたアカデミー(ロイヤル・ソサエティ)(王立協会)が生まれることになったわけである。
そしてこのころになると、自然研究をひそかに行う傾向が強かった初期の会員の多くは死亡し、新しい世代の会員の考えは以前とは著しく違うものになっていったという。その表れとして、ひそかな研究という事を好まなかった建築家のクリストファー・レンが、1663年にフリーメーソン協会の上級監督者、1666年に本部長代行そして1685年には本部長の地位についていることがあげられる。つまりニコライはここで、従来の秘密のヴェールを脱いで、より開かれた組織へと変質したことを強調しているのだ。そして1723年にフリーメーソン憲章が、有名な物理学者で本部長代行であったデザギュリエによって書かれ、さらに1725年にパリにフランス最初の支部が設立されたことを記している。そしてこれ以後この協会は大々的に発展し、それに伴い著しい変貌をとげていった、との記述でニコライのフリーメーソン成立史は終わっている。
第二部の概要
続いてニコライはその翌年の1783年に、その第二部を刊行している。これは三章からなっているが、まず第一章「テンプル騎士団の秘密に関するアントン氏の研究について」は、ヴィーラント編集の雑誌『ドイツ・メルクール』に掲載されたニコライ作品への批判的論文に対する再批判である。第二章「テンプル騎士団への弾劾及びその秘密に関しての匿名氏の反論について」は、同じ雑誌に掲載された別の論文へのニコライの対応である。そして第三章「フリーメーソン協会の成立に関する匿名氏の反論について」は、同じ匿名の人物に対するこのテーマに関する再批判である。ここではこれらの著作の内容に立ち入ることは避けるが、ニコライに限らず啓蒙期の知識人の間では、こうした論争が絶えず行われていた、という事だけをここでは述べておくことにしよう。
ニコライがこれらの著作を発表したとき、彼はまだフリーメーソン協会の会員であった。それだけに彼に対する圧力は、陰に陽にいろいろあったようであるが、それだけに一層歴史研究に当たっての客観性への彼の努力は、称賛さるべきであろう。ニコライの試みはフリーメーソン史の「脱神話化」にひとしく、その意味で「啓蒙的目標」を追求したものであったと言えよう。
B 『 薔薇十字団及びフリーメーソンの起源と歴史に関
する所見』
本作品成立の経緯
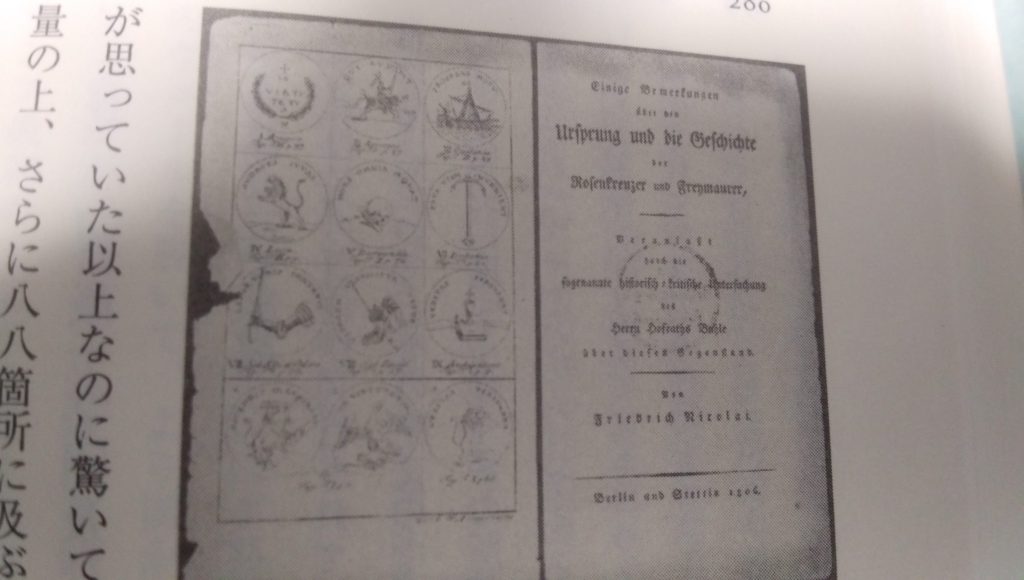
『薔薇十字団及びフリーメーソンの起源と歴史に関する所見』
これは先の著作が刊行されてから実に23年後になって発表されたものであるが、ニコライはこの作品の成立事情について、その序文の中で詳しく述べている。まず本書の正式な表題は『薔薇十字団及びフリーメーソンの起源と歴史に関するいくつかの所見。このテーマに関する宮廷顧問官ブーレ氏の、いわゆる歴史的・批判的研究に触発されて』(1806年)である。この副題の中に本書執筆の動機が示されているわけである。
ただ執筆に至るまでにニコライは、多少の紆余曲折を経験している。そうした事情について序文の中で記している。それによるとブーレ氏の著作が1804年の秋に刊行されたとき、ニコライはすでにこのテーマについては知り尽くしているので、わざわざ読むことはしなかったという。そして少し後になってこれへの書評が出た時はさすがに目を通した。そしてブーレ氏が自分の本をいろいろ利用しておきながら、あたかもそれを本人の自説であるかのように述べ、あまつさえ自分に対して論争を挑んでいることを知った。それでもブーレ氏の本を精読するのは時間の無駄であるので、あえてしなかったという。その理由としてニコライは、次のような譬えを用いている。「文学の世界には、乳を飲ませてくれた乳母のことを、後になって殴りつけるようなぶしつけな子供がいるものだ!」
しかしその後、『ドイツ百科叢書』の協力者の一人から、このまま放置しておくとブーレ氏が行っているニコライ非難を認めてしまうことになるので、まずいのではないかと言われ、ニコライもようやく重い腰を上げたという事である。こうしてニコライは1805年の10月末になってブーレ氏の著作を読み、自分に向けられた非難・攻撃が思っていた以上だったのに驚いて、本作品を書いたという訳である。この作品は本文180頁とかなりな分量のうえ、さらに88か所に詳細な註が、67頁にわたってついている。一度取り組んだ仕事は中途半端に済ませないニコライの粘液質の性格が、そこにはよく表れているといえよう。
執筆の動機とブーレ氏への反論
ニコライはブーレ氏の著作への批判ないし所見を述べる前に、まずその本文の50ページほどを費やして、どのような動機から自分がこのテーマに取り組むようになり、その後長年にわたって、いかに深くこの問題を研究してきたかということについて詳述している。その冒頭で彼は、1781年の南ドイツ旅行の際にミュンヒエンのアカデミーの会員に推薦されたことのお礼として、それまでの研究をまとめて『テンプル騎士団に対してなされた弾劾に関する試論』を提出したことを記している。またその付論として添えられた『フリーメーソン成立史』が生まれたのも、アクチュアルな動機によることが明らかにされている。つまり自分が所属していたフリーメーソン協会の中に、とりわけ1775年ごろから「未知の上位者への盲目的服従」や「秘密教団」的色彩が強化されるようになったことに、危機感を抱いてその源をたどることを決意して書いたというわけである。その後ニコライの筆はこれらの著作の具体的な内容に触れながら、当時彼の周辺で目に付いた「黄金薔薇十字団」のことにも及んでいる。
そしていよいよニコライはブーレ氏の著作に対して、具体的に反論を加えていく。そこでは、このテーマについては自分は第一人者であるという自信に満ち溢れ、微に入り細を穿ったやり方で、個々の問題に深く立ち入っている。それはまさに圧巻といえるものであるが、ここではそれに触れることはできない。ただそこで展開されているブーレ氏の作品に対する批判の重点は、「自ら称している歴史的・批判的研究」に向けられていて、それがいかにその名に値しないかを、これでもか、これでもかといった調子で検証しているのだ。
長年歴史研究に携わったニコライであったが、円熟の境に達した晩年に書かれた本作品の中には、彼の歴史方法論が十二分に記されていることは、注目に値しよう。
(4) 文化史上及び言語史上の著作
『古代及び近代における鬘(かつら)の使用について』
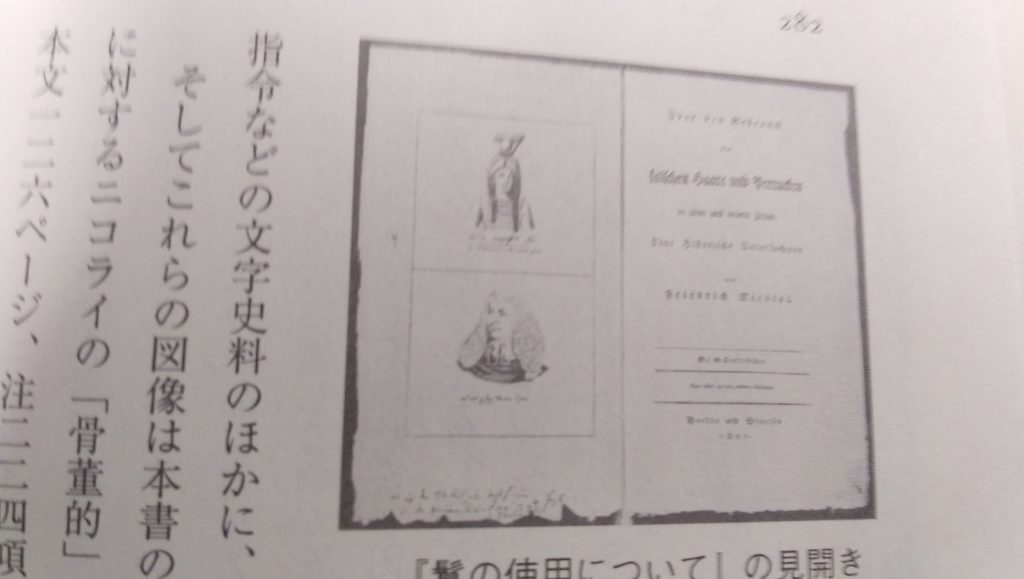
『古代及び近代における鬘(かつら)の使用について』の見開き
ニコライは言語の歴史にも興味を持っていて、様々な機会に散発的にその成果を発表しているが、まとまった著作にはなっていないので、ここでは彼の文化史上の主著ともいうべき『古代及び近代における鬘(かつら)の使用について。一つの歴史研究』(1801)を取り上げることにする。
この作品はもっぱらニコライ自身の資料研究から生まれたものである。その扱う時代は、ギリシア・ローマの古典古代時代から、ヨーロッパの中世・近世を経て、彼が生きていた十八世紀末までとなっている。史料としては、ギリシア・ローマの学者・作家の著作、キリスト教の教父たちが遺した言葉や説教、教会会議の決議、中世の記録史料、領邦君主の勅令や税に関する指令などの文字資料のほかに,硬貨やメダル、記念碑に描かれた図像などが用いられている。
そしてこれらの図像は本書の中に掲載されていて、本文への読者の理解を助けている。この作品は、歴史事実に対するニコライの「骨董的」ともいうべき、細部に対する強い興味と関心によって彩られている。そのためか、本文126頁,註224頁項目53頁、図像66点・17頁という構成になっている。
ギリシア・ローマ時代
まず前半のギリシア・ローマ時代については、我々にもおなじみの学者や作家、皇帝、英雄などが、いろいろ登場している。アリストテレス、クセノフォン、アリストファネス、トゥキディデス、オヴィディウス、ヴィルギリウス、ホラティウス、アプレイウス、キケロ、イシドールなどである。これら古代の作家や学者の著作から、頭髪や鬘に関連した叙述がギリシア語とラテン語のままで引用され、さらにラテン語の聖書の記述も援用しながら、それらに自らのコメントを記し、叙述を進めている。またカエサル、ネロ、カリグラといった皇帝たちが描かれた硬貨の図像も用いられている。そうしたコメントや叙述の中から興味深いものをいくつか拾い上げて、ご紹介することにしよう。
まずローマの詩人マリニウスの占星術風の詩の一部が引用され、「プレアデス星団(すばる)の下に生まれた人は、鬘をかぶるよう定められていた」と歌われているが、この習慣はギリシアから来たものではないかとニコライは疑問を呈している。また同時代のドイツ人ヴィンケルマンが「エジプトのイシス神の頭部を描いた図像から、これこそ史上初の鬘についての図版である」と書いているのを引用して、自分もそれを信じるとしてその図像を掲載している。さらにローマ人の場合、鬘は禿頭を隠すためだけではなく、皇帝ネロやカリグラなど有名人が顔を悟られないために使用していたとも書いている。そしてローマの仇敵カルタゴにも鬘は知られていて、歴史家ポリュビオスによれば、ハンニバルは鬘をたくさん持っていて、やはり変装用に用いていたとしている。
いっぽうローマ人の女性は髪型にも大変気を使っていて、たいていの女性が正真正銘の鬘をかぶっていたという。その際彼女らはゲルマン女性の金髪をたいへん好んでいて、それらを取り寄せていたという。そして「公娼はブロンドの鬘、堅気の娘や中年女性は褐色や黒色の鬘をかぶっていたとの説をしばしば見受けるが、そうしたことを立証する史料は見当たらない」としてニコライはその説を退けている。
語源的考察と中世
次いでニコライは十八世紀当時「鬘」を意味していた”Perrucke” という言葉がいつごろから使われていたかという語源的考察に入り、「この言葉が十六世紀以前に使用されていたと考えることは難しい」としている。言葉の歴史にも強い興味を抱いていたニコライは、この語源的考察に16ページも費やしている。
この後ニコライの筆は中世に入る。そこではビザンティンの僧侶ゾナラスの言葉を引用して、「この時代オリエントのキリスト教徒は好んで鬘をかぶるために、髪の毛の多くを刈り取った。とりわけそれは男性に多く見られた。ある者は自分の黒髪 を金色ないし金褐色に染めた。そしてそれを真夏には漂白するために、太陽にさらした」と書いている。いっぽう十三世紀のスコラ哲学者アレキサンダー・フォン・ハレスは、鬘の使用に強く反対しているが、当時フランスやその他の国々で、たぶん鬘が使用されていたのであろうと書かれている。
近 世
やがてニコライの筆は近世に進み、十六世紀にはオランダ、フランス、ドイツなどでは男性が鬘をかぶることはたぶんなかったようだ、と書いている。そしてこの時代の男性は一般に髪を短くしていたが、エラスムス、カルヴァン、ツヴィングリをはじめとする学者方は、縁なし帽子をかぶっていたとして、それらの図版を掲載している。それに対して十六世紀から十八世紀にかけて、ヨーロッパの女性の間では、鬘が用いられていたとしている。そして十六世末にイギリスのエリザベス女王は、65歳の時金髪の鬘をかぶっていたと述べられている。
その後ニコライは、男性の間で鬘の使用が流行するようになったのには、何か特別なきっかけがあったに違いないと考察し、それは十六世紀の最後の四分の一の時期に起こったと書いている。それはフランス国王アンリ三世が、性病にかかって髪の毛の多くを失ったため、それを隠すために鬘をかぶったことが、きっかけであったと述べている。それからニコライはイギリス、スペイン、イタリア、フランス、オランダ、北ドイツにおける事情を考察した後、十七世紀後半のルイ十四世の時代に、鬘の栄光の時代が訪れ、国王自らがかぶり、それを宮廷人が真似をし、かくして鬘をかぶる習慣は、ヨーロッパ中に広がっていったとしている。
十七・十八世紀のドイツ
最後の部分でニコライは、自分の国ドイツにおける鬘事情について詳述している。この時期の鬘の使用は、十七世紀の最後の三分の一の時期に、フランスから南ドイツやイギリスに普及し、さらにイギリスから特別な関係にあった北ドイツのハノーファーやブラウンシュヴァイク地方に移っていったという。ベリリンにおいては、1675年以降、政治家、法学者、医者などがとても大きな鬘をかぶっている図版が存在するが、十七世紀にはまだほとんどすべての牧師や学校教師は鬘を使用していない。ところが十八世紀の最初の四半世紀には、ドイツの全プロテスタント地域(主として北部及び東部)において、すべての聖職者、学校教師が鬘をかぶるようになっていた。
この傾向は当然のことながら、地位や身分が高まるほど、早い時期に見られる。すでに1656年に、プロイセン大選帝侯の鬘姿が硬貨に刻まれているが、彼はたぶんその妃ルイーゼ・アンリエッテの影響を受けて、この流行を取り入れたのであろう、とニコライは述べている。そしてその息子たちカール・エーミール、フリードリヒ(のちのプロイセン王国初代国王フリードリヒ一世)、ハインリヒなどは、二歳から十歳の間に鬘をかぶせられていたのだ。幼少のころから鬘をかぶっていたフリードリヒ一世は、成人後の肖像画でも立派な鬘姿で描かれている。またプロイセンの宮廷にしばしば出入りしていた有名なが学者ライプニッツも、大きくて立派な鬘をかぶっていたわけである。
こうした伝統を破ったのが、軍人王と呼ばれていたプロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム一世であった。彼は1713年の国王就任の日に、鬘をかぶっていた88人の侍従及びその他大勢の宮仕えの人々を解任し、自らもその数か月後に鬘を脱ぎ捨てた。そして質素な軍服に身を包み、髪は束ねて後ろで黒紐で結んだ。この弁髪は当時、国王としては全く異常な姿であったため、ヨーロッパ中で注目を浴びたという。この国王はさらに1717年にには、従来からあった鬘税を廃止した。これに関連してニコライは、「大きな鬘と一緒にフリードリヒ・ヴィルヘルム一世は、その他すべての奢侈と儀式も捨て去った。それらは莫大な時間と金を費やすものであったから、国土改革以上に重視されたものであろう」とのコメントをつけている。とはいえ彼の統治下にあっても、あらゆる身分の男性はなお、鬘をつけたままであった。
そしてその後のフリードリヒ二世の統治前半には、プロイセン国の男性は若者に至るまで鬘をかぶるのが普通であったという。1740年にはハレ大学では、教授といわず学生といわず、鬘をつけていない者を探すのは大変であったのだ。またプロイセンの軍人の間では、七年戦争(1756-63)のころまでは先代国王によって導入された小さな弁髪鬘がん見られたが、大臣や政府高官は大きく立派な鬘をつけていた。ニコライの知人のフルート奏者クヴァンツは、1720年には立派な鬘をつけていたが、1760年にはプロイセン国王の首席音楽奏者として、当時フランスから伝わってきた、後ろに垂らした髪を袋になったリボンで包む「袋鬘」をかぶっていたという。その後ニコライの筆は、フランス革命時に見られた髪型の流行の変化に触れ、それをもって「鬘の歴史」の結びとしている。
3 ニコライの歴史方法論
前述したように、歴史研究者としてのニコライの側面に注目して、最も詳しい研究を遺したのが現代ドイツの歴史学者ホルスト・メラーであった。その中でもメラーが特に力を入れて取り組んだのが、ニコライの歴史方法論であった。メラーはニコライの歴史関連著作について具体的に触れた後、彼の歴史方法論について、実に整然と体系立てて分析・説明している。そこでここでは、メラーの分析を要約した形で、紹介していくことにする。
(1) 史料批判と解釈
メラーはまず、「史料」の価値及びその評価方法に関するニコライの見解をただしている。それによると、すべての歴史著作の中でニコライは、集中的に資料研究を行ったという。そしてその一例として次のような具体例が挙げられている。「テンプル騎士団及びフリーメーソンに関する彼の研究を、事実に即さず、十分な史料的知識なしに攻撃したヘルダーに対して、ニコライは次のように反論した。<・・・根拠なき啓蒙、記録史料なしの研究的啓蒙は、啓蒙などではない>と」。
またテンプル騎士団の歴史研究に関してニコライに先行していた著作家たちのやり方を、彼は次のように批判したという。「ニコライは次にあげる言葉の中で、彼独自の原則をまとめている。<もし真実の歴史を述べようとするならば、歴史的証拠を出せないものについては、確実なこと以外には、主張してはならない。推測や仮説は歴史的証拠ではない。それらは史料不足の場合には、歴史の暗闇の中に何らかの痕跡を見出す手がかりになるかもしれないが、それは他の確実な情報と一致する限りにおいて、有効なのだ>」。
次いでメラーはこれに関連して次のように述べている。「要するにこの文章はニコライの歴史叙述の本質を表明しているものである。歴史著作の基礎としての同時代史料、特殊なコンテキストにおけるそれらの解釈、史料によって証明できるものと単なる憶測や仮説との違い、そして年代研究と因果関係の分離。これらもろもろの問題点は、たしかに同時代史料に権威を与えるものではあるが、それでもって学問的歴史叙述の諸問題が解決された、と彼が考えていたわけではない。むしろ彼は現代歴史学のさらなる構成要素である次の点も認識していたのである。つまりまず第一に徹底した<史料批判>、そして第二に<史料解釈>の問題を論じたのである」
この関連でメラーはさらに続けている。「ニコライがその<フリードリヒ二世の逸話>及び<ツィンマーマン氏に関する所見>の中で、出来事に直接関与した同時代人に部分的に依拠せざるを得なかった。そしていくつかの逸話の真実性について、直ちにその出所を調べた時、証人の供述の持つ問題性を認識した。それらは一般に後から勝手に付け加えられたり、あるいは削られたりして、結局は雪だるま式に膨らむか、霞のように消え去るかして、確かなものは何も残らないのだ。<ツィンマーマンに関する所見>の中で、彼は例えば文体調査を援用したり、性格上の特徴を考えたりして、ある歴史上の人物の特定の供述が、ツィンマーマンが主張したように、本当に本人の口から出たものかどうか、調べようと試みた。そしてツィンマーマンは史料評価に当たって、<慎重に、歴史批判の立場から作品に取り組まねばならなかったし、少なくともいわゆる信頼性に対する彼の理由付けを明瞭に表明するか、もしくは信頼できるものではない、と表明すべきであったのだ>と非難した。史料批判に対する同様の発言は、ニコライの歴史著作のいたるところに見られる」
(2) 仮説の構築
次いでメラーは史料が不足した状況での仮設構築の問題を扱っている。「ニコライがその独自の研究において、とりわけフリーメーソンとテンプル騎士団の歴史に関する研究において、しばしば指摘しているように、史料を巡る状況はしばしば、調査すべき問題に対して間違いなく一次史料から説明できるとは限らないので、歴史家は類推を含めた仮説の構築を必要とするのだ。ここでは史料評価に対するのと同様に、その仮説は立証された事実や確実な史料と矛盾してはならない、という原則が当てはまる。史料研究と仮設構築を結び付けるニコライのやり方は、次の引用の中に表明されている。
<人は様々な原則の蓋然性と非蓋然性について、既知の事柄との慎重なる比較によって、判断することができる。とはいえ全く記録史料がなく、純粋に仮設だけから成り立っている歴史というものは、まずないと言いていい。(しかし)記録史料のみによって構築された歴史というものも、ごくわずかか、あるいはまったくないとも言える。・・・もし昔のことや新しいことについて、二、三の信頼すべき語り手の供述が食い違っていたとするならば、その時は最も蓋然性の高いものを選ぶか、もしくは様々な情報を総合しようとすべきではないのか? それはただ仮説を検証することを通じてのみ可能なのだ。仮説の価値は疑う余地がない。しかもまさにそこでこそ、本当の史料批判が適用されねばならないのだ。
(3) 説明と理解
さらにメラーはニコライの歴史叙述の根本に触れて、次のように書いている。
「ニコライにとっては常に、物事が如何にして生起したか、それはどのようなものであったか、歴史的人物の行動はどのような動機でなされたか、そしてその動機はどのように説明されうるか、という事が問題なのであった。これはまさにのちのランケの歴史研究に対する批判実証的な基本的態度と共通するものだといえよう。メラーはさらに論を進めている。
「これらの問題 に関しては、彼は実用的手法の信奉者であったが、これこそは啓蒙的歴史叙述の不可欠の要素だったのであり、またこれはポリュビオス(古代ギリシアの歴史家)が創り出していたものでもあった。・・・その目的は、歴史上の出来事の原因とその内的連関を発見することであった。そしてさらに実用的歴史叙述は、後世の人々に教訓を与えることを課題としていた。歴史にこうした目的を与えることについては、ニコライのほかにも、何人かの名前を挙げるとすれば、カント、メーザー、ガッテラー、ヨハネス・ミュラーなども、このことを公言していたのである」。
次いでメラーは、ニコライが歴史上の出来事の因果関係の分析だけでは満足せずに、歴史上の人物が抱いていた意図というものにも注目したことに触れている。それはその人物の行動を説明すると同時に、歴史的対象を時間的へだたりと、未知のものの個別的相違に基づいて「理解」するためだという。その意味でニコライは、ツィンマーマンに対して、まさにフリードリヒ大王の視点に立たねばならない、としたのだ。その関連でメラーは次のように続けている。
「・・・テーマを経済史的・人口史的問題ならびに宗教史的・文化史的問題に拡大することによって、原因と結果のシェーマでは部分的にしかとらえることができなかった歴史的生活や個別的状況の複合体が生まれたのである。・・・過去のなかには数多くの歴史的主体と名の知れない原因が存在し、数多くの歴史的問題とあまりにも多くの未知の存在があった。原因と結果のカテゴリーの助けによる単なる因果論では、個々の原因を十分説得力を持って説明することはできないのだ。・・・なぜならその超時間的・論理的性格は、歴史の特殊性を適切に表現するのに向いていないからだ。
・・・ニコライは、彼の著作の数多くの個所で、時代的制約に縛られた自己の基準を、過去の時代に適用することを批判した。例えばフランス人のミラボーはその著書『プロイセン王朝』の中で、フリードリヒ大王の経済政策を、その重商主義的原理によらないで、自己の重農主義的前提に立って判断したため、誤解したのだと、ニコライは非難している」。
この後メラーは次のような言葉で、この項目を結んでいる。「疑いなくニコライは、歴史の独自性や・・・歴史はそれ自体の価値を持つという考えを理解していた人物であった。そしてそのことによって、彼は新しい認識に道を開いたのであった。<それが次第次第に現在に至るまでどのように変化してきたのか、そしてまた各時代の習俗やその段階的発展あるいは急激な変化など>を把握しようとした彼の努力は、歴史的思考の二つの決定的な前提ー歴史事象の特殊性と全体性ーを把握すべくニコライを運命づけたのであった」。
(4) 客観性の原理
メラーは、この客観性の原理をニコライが歴史叙述の義務的目標とみなしていたとして、次のように述べている。「研究対象に対する時間的な距離がニコライの歴史的思考において、質的な距離になった。この認識からニコライの歴史研究の最後の中核的思考は刺激を受けたのだが、それはつまり客観性の原理なのである。・・・ニコライは歴史叙述者に対して、次のように要求した。<歴史叙述者は、抑制された想像力と並んで勤勉さ、真実への愛好そして公平さを持たねばならない。こうしたことこそが、その者にとって、正しい情報を探し出し、慎重に点検し、その後で出来事を、いかにそれが本当にこれらの情報によって規定されているのか、厳密に叙述し、その際それに何か付け加えたり、差し引いたりしないことに役立つのだ>
この文章によってニコライはすでに、ランケが後に歴史叙述の役割として規定したこと、つまり<それは元来どうであったか>という事を叙述するという立場に近づいていたのだ」。ニコライがこのことを強調したのは、当時啓蒙主義陣営の内部でも外部でも、言論活動や学問研究の場において、客観的というよりも党派的な実例がことかかない、といった状況にあったからである。
そのためこの時代の歴史研究の内部で、そもそもこうした要求を掲げたこと自体が重要なのである、と述べてメラーはこの点を高く評価している。しかし同時にニコライが客観性の基準を問題にしなかったことを、彼の哲学的思考の限界が示されたものとして、次のように批判しているのだ。「いかなる経験的認識も認識対象の外にある前提によって規定されているという事、そしてまた<真理への愛>や<公平さ>への要求だけでは<客観的>認識を保証するには不十分であることを、ニコライは考えなかった。・・・カントの認識批判を跡付けることは、ニコライには不可能であった。彼は生涯カントと論争を続けたが、熟考の不十分な経験主義の信奉者であり続けた」
このように哲学的思考がニコライの弱点であった事を指摘したメラーであったが、それが歴史研究者としての資格の欠如を意味するものでない事は、メラーも十分認めている。そこには歴史家と哲学者の立場の相違という、根本的な問題が横たわっているのだ。同じ歴史家であるメラーはこの点を十分理解していて、最後にこの項目を次のように結んでいる。「客観性基準についての立ち入った議論には欠けていたものの、ニコライがそもそもこの要求を掲げたこと、中でも彼がその客観性をその研究と原理的言及の中で、実際的作業のためのに明らかにし、未来志向的基準を含んだ方法論の構築とむすびつけたことこそは、歴史叙述の学問性にとって大きな収穫であったのだ」。
