まえがき
私はこのブログにおいて、2020年3月以来、月に1回のペースで、自分の研究テーマの中核をなすヨーロッパの出版文化史についてずっと紹介してきた。まずヨーロッパの源流ともいえるギリシア・ローマ時代の書籍文化について詳しく紹介した。次いでヨーロッパ中世の書籍文化について簡単にふれた後、15世紀におけるグーテンベルクの活字版印刷術の発明とその伝播についてかなり詳細に書いてきた。この時以降、それまでの筆写による書籍文化から出版文化へと変わったわけである。そしてその出版文化の歩みを18世紀までたどり、前回2021年12月には、「18世紀ドイツ啓蒙主義と文学市場の誕生」について紹介した。
さて今回はその18世紀ドイツ啓蒙主義に関連した重要人物であるフリードリヒ・ニコライについて取り上げることにする。
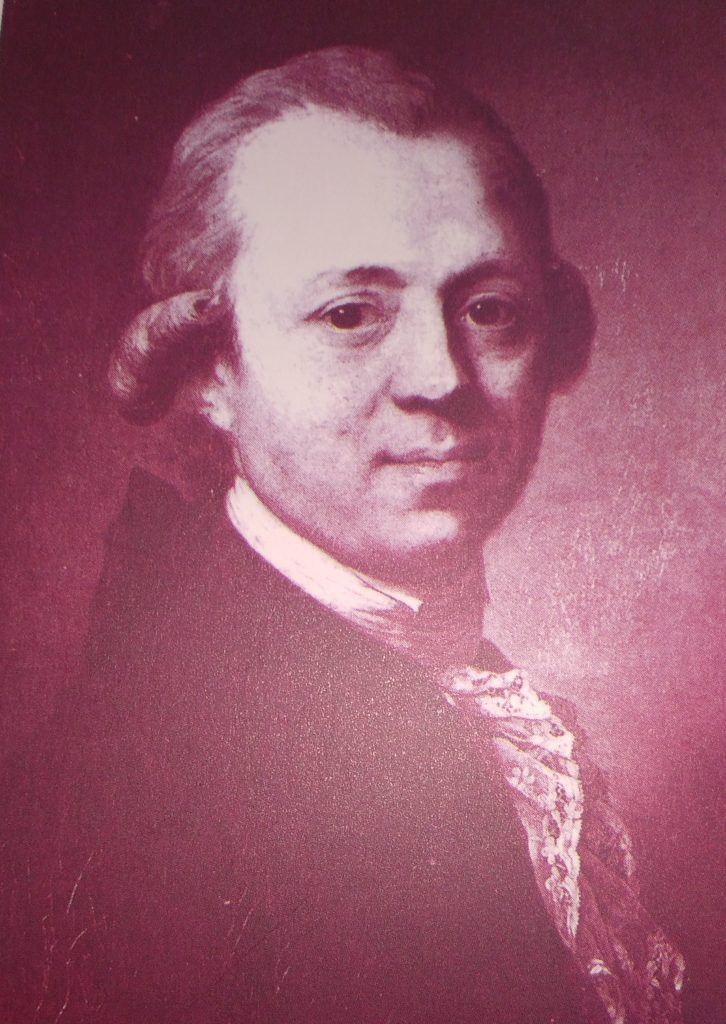
フリードリヒ・ニコライの肖像
フリードリヒ・ニコライとは何者か?
おそらく皆様の中で、フリードリヒ・ニコライ(1733-1811)についてご存じの方は、きわめて少ないと思われる。この人物は18世紀ドイツの啓蒙知識人で、同時に大出版業者なのであるが、わが国では、これまでドイツ文学やドイツ思想の専門家がその名前を知っているぐらいであった。
しかし私はドイツの出版史を研究する過程で、この人物の存在を知ったわけである。つまり『ドイツ出版の社会史~グーテンベルクから現代まで』(三修社、1992年12月発行)の原稿を執筆している時であった。その第4章「18世紀半ばから1825年まで」を書く過程で、18世紀ドイツ書籍史研究家であるパウル・ラーベの研究に出会った。ラーベはニコライ書店の在庫目録に基づいて様々な角度から分析しているのだが、私はこの研究に依拠して、啓蒙主義時代のドイツの出版状況を記述したわけである。その時以来、ニコライという人物に強い関心を抱くようになった。
そして我が国においてニコライがどれぐらい一般的に紹介されているのか知るために、戦後発行された主な百科事典にあたってみた。しかし多くの百科事典にはニコライについての記述が見当たらなかった。ただ平凡社の「世界大百科事典」の場合、1981年の版にはまだないのに、1985年版からは、その名前を独立した項目として取り上げている。そしてそこには次のように記述されている。「ドイツの出版業者、著述家。ゲーテ、シラー、カント、フィヒテらを攻撃したため、頑迷な啓蒙主義者と見みられがちであるが、啓蒙主義の指導的な雑誌の刊行者、ベストセラー作家、批評家として、その多角的な活動は、ドイツ18世紀文化史に大きな足跡を残した。レッシングやM・メンデルスゾーンの助けを得て、ベルリンの啓蒙主義運動の組織者として活躍し、文化の媒介者の役割を果たした。(岩村行雄)」
この短いが、要を得た記述によって、この人物の業績の概要は理解されよう。ニコライの名前が日本の百科事典にも取り上げられるようになったという事は、実は近年ドイツにおいてニコライに対する再評価の動きが盛んになってきたことの、まさに反映だといえるのである。
私のニコライ研究の経緯
さてニコライとの私の二回目の出会いは、以前勤めていた日本大学経済学部の図書館が、1995年に、ニコライが編集していた書評誌『ドイツ百科叢書』のオリジナル版全135巻を購入するにあたって、推薦状を書いたときであった。幸いこの雑誌は購入され、私としてはいつでも利用できる状況になった。

『ドイツ百科叢書』
(全135巻のうちの2巻。右側中央に描かれているのは、
古代ギリシアの詩人ホメロスの胸像)
これが契機となって、私はニコライについて論文を書こうという気持ちになり、関連の文献や資料の収集に全力を傾けることになった。とはいえニコライについて日本語で書かれた論文はわずかで、本格的な研究著作は皆無であった。しかしドイツにおけるニコライ研究はかなり進んでいて、その成果もどんどん刊行されていた。新しいものは国内の洋書輸入書店を通じて購入することができた。ただ十年・二十年以上前に発行された図書などは、このルートでは無理なので、以前からたびたび訪れていたフランクフルト・アム・マインの「ドイツ書籍出版会館」内の図書館に行き、必要な文献・資料をコピーした。
そしてまた当時ベルリンに「ニコライ出版社」が存在していることも分かった。そこで早速ベルリンに飛び、都心部にある同出版社を訪ねた。ニコライは子供たちに先立たれ、血のつながった後継者はいなかったのだが、ボイアーマン氏が社長をしていて、幸いなことにこの人物に会うことができた。同出版社では当時なお、ニコライ関連の図書も刊行していた。そのうえベルリン郊外にある社長の自宅には、ニコライ関連の初版本など貴重図書を含めた私設文庫があった。私はそれを利用することができ、貴重書はコピーを取らせていただいた。また一般的な性格の文献・資料は数点、譲り受けることができた。
さらにこのボイアーマン氏には、ニコライが熟年期から晩年にかけて住んでいた邸宅にも案内していただいた。そこは統一ベルリンの中心部(ウンターデンリンデン大通りのすぐ近くのブリューダー街)に位置していて、建物の外壁には「ニコライ・ハウス」という銘板が貼られていた。建物の内部は、東独時代には政府関係の事務所として使われていたというが、その時は空き家になっていた。

ニコライ・ハウスの外観
こうしてある程度の準備ができた段階で、私は順次論文を書き始めた。ただ多方面な活躍を見せていたフリードリヒ・ニコライについて、はじめのうちはその全貌がつかめなかった。しかしそれまでドイツ出版史を研究していたところから、まず出版業者としての側面から入っていった。その結果、「出版業者としてのフリードリヒ・ニコライ」(1996年4月)と題する論文が出来上がった。これを書き終えた時、漠然とながらニコライの様々な業績を順次解明していこうという心構えが出来上がった。
そしてその後さらに、18世紀ドイツの社会文化史という大きな枠組みの中で、この啓蒙知識人がその時代において果たした役割、ならびに後のドイツ社会の変革に及ぼした影響について、明らかにしていこうと思うようになった。こうして先の論文を含めて7つの論文を、日本大学経済学研究会の『研究紀要』に発表していった。それらは
ー フリードリヒ・ニコライの『王都ベルリン及びポツダムについての記述』について。
ー フリードリヒ・ニコライの『ドイツ百科叢書』について
ー フリードリヒ・ニコライの生涯
ー フリードリヒ・ニコライとベルリン啓蒙主義
ー フリードリヒ・ニコライの『南ドイツ旅行記』について
ー 歴史研究者としてのフリードリヒ・ニコライ(2000年10月)
これらの論文が出来上がる前から私はこれらを素材にして、一冊の本を書きあげようと考えるようになった。その際各論文の間に重複していた部分は調整し、資料的な性格の部分は、巻末にまとめて資料編として掲載した。こうして完成した本が、『ドイツ啓蒙主義の巨人 フリードリヒ・ニコライ』(朝文社、2001年2月)である。
これから紹介していくブログの中身は、おおむねこの本に基づいているが、一般の読者向けに、やさしくかみ砕いて書くようにしている。
ニコライについての評価の変遷
<19世紀から第二次世界大戦までのニコライ評価>
19世紀の初めから第二次世界大戦ごろまで、ドイツの政治的、社会的傾向はおおむねナショナリズムに彩られてきたといえよう。そしてその一方文化的・精神的潮流としては、そうした政治や社会あるいは経済の動きから超然とした新人文主義や教養主義の流れの中で、文学、哲学、芸術、科学などの精神文化が花開いてきた。長い間ドイツは「詩人と哲学者の国」として、知られてきたわけである。
ニコライはゲーテ以下の作家や哲学者たちとその晩年に行った論争の結果、そうした人々から仮借ない非難を受けた。そしてその後いま述べたような時代状況が続く中で、そうした評価を受け継いだ文学史家や哲学史家によって、軽蔑と酷評のまなざしで眺められてきたのであった。つまりその間ニコライは、もっぱら文学史や哲学史の枠組みの中で、低い評価に甘んじなければならなかった。そうした状況の中では、ニコライの生涯や業績に客観的な立場から取り組むのが困難であったことは、容易に想像がつく。
しかし何事にも例外があり、19世紀の末にニコライないし啓蒙主義を高く評価する人物もいた。その一人がテュービンゲン大学の事務局長を務めていたグスタフ・リューメリンであった。彼はニコライの旅行記のシュヴァーベンに関する部分について1881年に論文を書いた。そしてその中で「ニコライは出版の自由、民衆教育の拡大と時代への適応、農業及び産業における規制撤廃、ドイツの学問の大衆化などのために闘った、実際的な思想家であった」と書いている。つまりそこでニコライの時代に先駆けた先進性を指摘しているわけである。
もう一人は著名なプロテスタント神学者のエルンスト・トレルチュであった。彼は啓蒙主義を高く評価した論文(1897年)の中で、ニコライの小説に言及し、またベルリン啓蒙主義の中心人物としてのニコライとその書評誌『ドイツ百科叢書』にも触れている。この神学者については、後でもう一度触れることにする。
次いで第一次世界大戦後になると、19世紀の精神潮流にも変化がみられ、ニコライ評価もかなりバランスの取れたものとなってきた。そのためこのころ書かれた18世紀ドイツの文化・思想に関する著作の中では、ニコライについて長所と短所の双方を取り上げて論じられている。例えば文化史家マックス・フォン・ベーンはその『ドイツ18世紀の文化と社会』の中で、次のように記している。「かわいそうにフリードリヒ・ニコライは<頑迷なるベルリン人>の原型にされてしまうという運命に甘んじなければならなかった。つまり、せかせかした落ち着きのなさ、味気ない考え方と尊大な饒舌に加えて、万事についての知ったかぶりの故にである。しかしこの<文明開化>の使徒は、その欠陥すべてを認めたうえで、なおかつ彼の時代に不可欠の人間であったという事ができよう。・・・啓蒙主義を勝利に導いたことがそもそも一つの功績であるとすれば、この名声のかなりの部分が、フリードリヒ・ニコライに帰せられてしかるべきである。彼は存命中にこの名誉を勝ち得たが、1811年に七十八歳で死んだときには、この名声はすでに過去のものとなってしまっていた。」
同じく文化史家エーゴン・フリーデルはその大著『近代文化史』の中で、ニコライに一項目を与えて、次のように評価している。「実直で知識豊かで、賢く才能のあるこの男は、有名な書店主の家柄に生まれ、商人と文士のあいの子のような人物であり、時代の思潮をくみ出して発表する才能にたけていた。だが、その一方では、彼自身の凡庸さとひとりよがりによって、送られてくる原稿を編集するために、たいそう露骨な結果をもたらした。そのうえ・・・偏狭な合理主義のために、高慢で浅薄な上げ足取り批評の、世にも名高い模範例となってしまった。・・・そうであるにもかかわらずニコライの名誉を回復してやりたいと思う。・・・ニコライは生粋のベルリン人であり、論理的で即物的であろうとする善意に満ち、月並みな文句や現実離れした空想や山師的な言行にはたいそう強い不信感を抱き、極めて堅実で、非常に勤勉で、すべての物事に関心を寄せ、常に諧謔的精神を働かせる人物であった。」
<第二次世界大戦後のニコライ再評価>
第二次世界大戦後になると、1949年、分割されたドイツの西側にできた西ドイツ(ドイツ連邦共和国)においてすべての状況が変わった。東側にはソ連の影響を強く受けた社会主義の東ドイツ(ドイツ民主共和国)が生まれたが、この国のことはこの際置いておく。さて西ドイツでは、精神文化の領域においては、1960年代に入って、新しい世代が活躍するようになった。そして19世紀初めから第二次世界大戦まで続いてきた精神文化の潮流を見直す動きが出てきた。その中でドイツ18世紀史の再評価の動きが生まれてきたのだ。
ニコライ再評価も、まさにこうした流れの中で起きてきたのであった。初めはなお文学史的な潮流に棹さす形でモレンハウアーが、ニコライの作品中に見られる諧謔や皮肉に目をつけて、『ニコライにおける諷刺』という著作をあらわした。ついで70年代の初めにジヒェルシュミットは、ニコライの生涯と業績について、まとまった作品を著した。これはニコライの生涯をかなり忠実に描くのと同時に、啓蒙主義者としての業績を、主にその文学的な面に即して評価・叙述している。そしてその出版活動についても、なお一般的な評価にとどまるとはいえ、肯定的にとらえている。
いっぽうニコライ再評価のうえで画期的な役割を果たしたのは、ドイツ近現代史の歴史家ホルスト・メラーであった。彼は1974年に600頁を超す大著『プロイセンにおける啓蒙主義~出版者、ジャーナリスト、歴史叙述者 フリードリヒ・ニコライ』を刊行した。ここでメラーはニコライという人物を通じて、プロイセン啓蒙主義の全貌を余すところなく、描いているわけである。そしてこの作品は歴史家によって書かれたニコライに関する本格的な研究書なのである。
つまり従来の文学史的な評価から離れて、ニコライのジャーナリスト(時事評論家)並びに歴史叙述者としての側面が強調されている。そしてベルリンないしドイツの啓蒙主義の仲介者として果たしたニコライの大きな役割が明らかにされているのである。そこには歴史家としてのメラーの鋭い批判的な見解が随所にみられる。とにかく本著作によってニコライという人物に対する評価が、従来の文学史的な狭い枠組みから解き放たれ、ドイツ18世紀の社会史ないし文化史という大きな流れの中で行われるようになったわけである。その意味で私としても、メラーの著作には一方ならず世話になっているのだ。
<ニコライ生誕250周年記念行事>
こうして1960年代から始まった新しい動きは70年代を通じてさらに促進され、ニコライ研究はその生誕250周年に当たる1983年に、ひとつの大きな画期を迎えることになった。まずこの年にニコライの生誕地ベルリンにあるニコライ出版社から、生誕250周年記念論文集が刊行されたのである。そこには研究者9人の論文が掲載されている。まず今紹介したばかりのホルスト・メラ-の「歴史家としてのフリードリヒ・ニコライ」に続いて、、これも著名な歴史家であるルドルフ・フィアハウスの「フリードリヒ・ニコライとベルリン社交クラブ」、さらにW.マルテンスの「旅する市民」、パウル・ラーベの「出版者フリードリヒ・ニコライ」そして編集者でもあるB・ファビアンの「ニコライとイギリス」など、ニコライの多様な側面を専門的に研究した、優れた論文が収められているのである。
ちなみに18・19世紀の書籍出版史の専門家であるラーベは、翌年自らの論文集を刊行している。そこには「啓蒙のプロイセン出版業者フリードリヒ・ニコライ」のほか、「18世紀の出版業者」や「啓蒙のメディアとしての雑誌」などが収められているが、これらは私も利用させてもらっている。
生誕250周年記念行事としては、もう一つ、生誕地ベルリン(当時は西ベルリン)で催されたニコライの生涯と業績に関する大規模な展示会を忘れることができない。これは1983年12月7日から1984年2月4日まで開かれた。そしてこれを記念して、展示した書籍や雑誌、手紙、肖像画その他ニコライに関連した様々なものを、図録や写真として収録した立派なカタログ『フリードリヒ・ニコライ~生涯と業績~生誕250周年記念展示』が発行された。これには展示物の中から選んだ図版や写真に対して、詳しい説明書きが添えられている。また冒頭にはニコライの生涯と業績について簡潔に記した序文も掲載されていて、一般の人々のニコライ理解を助けている。ともかくこの展示会は、それまで一般にはあまり知られていなかったの思われるニコライについて、初めて大規模な形で紹介したものだったといえよう。
そのご1988年に刊行された三巻本の文学事典『文学ブロックハウス』でも、ニコライの項目には比較的大きなスペースが与えられ、「後期啓蒙主義の学問・文芸の仲介者」としての側面が強調され、最新の学問上の成果が反映されている。
その一方、ニコライの全作品を学問的に批判・吟味して復刻する動きも始まった。その一環として1985年からゲオルク・オルムス社の『ニコライ全集二十巻』(復刻版)の刊行が開始され、15年の歳月を経て、1999年に完結している。これは当時用いられていたフラクトゥーア体(いわゆるヒゲ文字)で印刷されていて、専門研究者向けのものである。
これとは別にニコライの作品を広く一般の知識人や、世界の人々に向けて紹介する意図をもったのが、1991年以来ペーター・ラング社から刊行されている全集『フリードリヒ・ニコライ。全著作、手紙、記録』である。これは現代人のために現代のドイツ文字に直して印刷されているが、文章の表記は18世紀のニコライの時代のままになっている。その代わりに、現代人のために極めて詳しい註と解説が付けられている。「ベルリン版」と称されてはいるが、発行地としては、そのほかニューヨーク、パリ、ヴィーン、ベルン、フランクフルトの名前が記されている。そこにはニコライないしドイツ啓蒙主義を欧米全地域に認知させようとする編集者・出版社の意図が感じられる。
ドイツ18世紀史研究の活性化
ところでこれまで述べてきた近年におけるニコライ再評価の動きは、1960年代から徐々にみられるようになってきた「ドイツ18世紀史研究の活性化」と密接に結びついていることは、言うまでもない。このことを最もよく示しているのが、1976年に刊行された論文集『ドイツにおける啓蒙主義、絶対主義及び市民階級』である。
ここには12の論文が収録されているが、その編集にあたった人物は、ドイツ人社会史家フランクリン・コービッチュである。その刊行の意図は、編集者が書いた巻頭論文「研究課題としてのドイツ啓蒙主義の社会史」の中に、明瞭に示されている。その中で彼は「啓蒙主義は哲学や文学のみならず、あらゆる生の領域を包括した改革運動であったので、個々に孤立した視点からでは十分な分析が行えない。その研究には諸学問の協力が必要である」ことを訴えた。そして「こうした観点から、この論文集には、歴史家、ドイツ文学者、哲学者、神学者、教育学者などの論考を集めたわけである。」と、まず強調した。
そして1975年3月に、18世紀ドイツ啓蒙主義の代表者であるレッシングゆかりのヴォルフェンビュッテルに、「ドイツ18世紀研究会」が設立されたが、これによってその方面の学際的研究が推進されることを、コービッチュは切に願ったわけである。それから彼は先の巻頭論文の中で、啓蒙主義の担い手の階層、改革プログラム、そしてドイツ啓蒙主義の到達範囲などについての体系的な研究が必要なことも、述べている。
さらに彼は、ドイツ18世紀史研究に欠かせない様々な課題を列挙して、すでに達成された成果として、収録したほかの11の論文を、要約した形で紹介している。これら11の論文はそれぞれ興味深いものであるが、ここでは18世紀ないし啓蒙主義を総体として扱っている3つの論文を取り上げて、その内容をごく簡単に紹介することにしよう。
<トレルチュの先駆的業績>
まず第一に紹介するのは、19世紀末のプロテスタント神学者E・トレルチュの論文「啓蒙主義」である。最初にトレルチュは、啓蒙主義の特徴を、次の3点に絞って述べている。
(1) 啓蒙主義は、それまで支配的であった教会的・神学的文化と対立した、ヨーロッパの文化と歴史の本来的な近代の開始を告げる思想である。(2)しかし啓蒙主義は学問的・思想的な運動に限られたものではなく、あらゆる生の領域で起きた文化の総体的な変革運動なのである。(3)その傾向としては、普遍的に通用する認識手段を通じて、世界を内在的に説明することと、一般に通用する実際的目標のために、生を合理的に秩序づけることがあげられる。
次いでトレルチュはこうした視点に立って、ヨーロッパ全体を視野に収めて、啓蒙主義の具体的な特徴を、さまざまな分野に分けて述べている。そこではオランダ、イギリス、フランスとの比較において、ドイツの啓蒙主義の流れを、具体的に叙述している。その意味においてドイツ啓蒙主義に関する古典的な論考なのであるが、19世紀末から第二次世界大戦までの民族主義隆盛のドイツでは、ほとんど顧みられなかったのではなかろうか。
<フィアハウスの18世紀見直し論>
第二の論文は、ドイツの著名な歴史家ルドルフ・フィアハウスが1967年に著した「18世紀のドイツ。社会構造、政治制度及び精神運動」である。フィアハウスは、その冒頭でハンナ・アーレントが1960年にレッシング賞を受賞したときに述べた「レッシングと我々の間には、18世紀ではなくて、19世紀が横たわっている」という言葉を引用している。つまり彼は、これまでドイツで18世紀が注目されてこなかった理由を、19世紀が立ちはだかってきた点に求めているわけである。しばらくフィアハウスの言葉に耳を傾けることにしよう。
「ドイツにおいてはとりわけ18世紀と19世紀の継続性という事が、問題となる。政治的な革命や社会的な変革は起きなかったとしても、その頃神聖ローマ帝国が崩壊し、帝国教会領、帝国騎士領、ほとんどすべての帝国都市領が消滅した。その結果ドイツの地図が大幅に塗り替わったのだ。そしてそれらのことどもが、ドイツ人の心の中に、フランス革命(注:1789年)以前の世界の状況は取り返しのつかない地点へと沈んでしまった、との感情を呼び起こしたのだ。さらに重要なことは、1770年から1830年の間の数十年間に起きた文学上・哲学上の黄金時代が18世紀にとって代わって現れ、後世の観察者の前に、どっかと立ちふさがってしまったことである。そして古典主義(注:ゲーテ、シラーに代表される)、新人文主義(注:W。フンボルトなど)、理想主義、ロマン主義、歴史的思考の開始などが、啓蒙主義的合理主義や自然法思想への反撃ないし18世紀の克服として理解されて来たのである。
啓蒙主義は一方的に合理主義的で、抽象的で、非歴史的で、非宗教的であり、この時代の国家は魂のない機械であり、教会は硬直化し、文芸はただ教訓的なだけだ、という観念が長い間、学問の世界と教育界で、支配的であった。さらにヨーロッパ(注:イギリス、フランス)の啓蒙主義からの転換こそが、ドイツ精神界の特別の功績であると認識され、またドイツ人の民族意識が1800年ごろの文化的な展開から、最も強い刺激を受けたという事情が加わる。
しかし最近になってドイツにおいても、18世紀に対する新たな関心が生まれてきている。そこでは18世紀は緊張に満ちた時代、数多くの変化とりわけ人間の意識の根本的変革の時代、そして進歩と危機の時代として描かれている。・・・いわゆる近代世界の根本的命題はすでに18世紀に論じられてきたし、近代世界の基本構造はすでに当時、その兆候が認められる、と主張できるのだ。しかし18世紀が与えた解答は、19世紀のそれとは異なるものであった。そして今日、啓蒙主義の時代の思想や思考スタイルに対する新たな理解や、新たな要求が出てきているのだ。」
<セインの啓蒙主義再評価>
第三の論文は、アメリカ人のドイツ18世紀史研究者トーマス・P・セインが1974年に著した「啓蒙主義とは何か~ドイツ啓蒙主義との新たな取り組みについての文化史的考察」である。この論文の導入部分でセインは、まず「18世紀の啓蒙主義がドイツにとって近代の始まりを意味することは、全く疑いのないところである」と書いている。しかしその後「18世紀は、ルネサンス以後のドイツの文化史において、研究され、評価され、理解されることが最も少なかった時代である」と付け加えている。
その理由として彼は、ドイツの諸領邦国家が16世紀半ばから18世紀半ばまでの200年間、政治・経済から文化・科学の研究に至るまで、イギリス、フランス、オランダに比べて、決定的な遅れをとったことを挙げている。そして「三十年戦争による恐るべき荒廃と非合理的な宗教論争が18世紀まで続いたため、精神的エネルギーと物質的な余力の大半を使い果たしてしまったわけである。神聖ローマ帝国内の諸邦分立主義は、諸邦が物事を全体としてみることや互いに協力し合うことを阻害してきた。そして17世紀末から18世紀半ばまでの精神生活の状況は、とりわけ学芸に対する支援の欠如、古い大学の哀れな実情、学校制度のみじめさの中に現れている」と述べている。
ところがこうした立ち遅れは18世紀末にワイマル古典主義やロマン主義が現れるに及んで、一挙に取り戻されたと言われてきたわけである。そしてセインによれば、「ドイツ人がその<古典>文化を誇りにし始めた19世紀以来、<啓蒙主義>は一般に悪い評判をとるようになった。・・・人々はやれやれという安堵のため息をつき、もはやその<前史>には立ち入って取り組むことをしなくなったのである。」という。
こうした状況が長い事続いた後「数年ほど前からドイツ啓蒙主義に対する新たな関心の喜ばしい兆候が見られるようになったきた」と、セインは話を続け、あわせて18世紀研究への期待を表明している。そして従来なおざりにされてきたことだが、18世紀ドイツの文化的成果として、経験的および数学的・理論的自然科学、国民経済学の研究、絶対主義的ではない新しいドイツ文学、近代歴史叙述と文献学の開始、人類学や比較民族学の研究そして旅行に対する新たな関心などがあげられている。
このように、次の19世紀に見られたドイツ文化の開花は、実はすでに18世紀の間に準備されていたことが、そこでは強調されているのだ。そしてさらにこうした18世紀の文化の研究にあたって、「文学史、哲学史、科学史など(個々の分野)の視点から観察するのではなくて、広い意味での文化史の視点から考察するようになれば、まさにその時こそ、重要で実り多い新たな成果が期待できるであろう」と、セインは付け加えているのである。
ニコライに対する私の評価
以上述べてきたように、フリードリヒ・ニコライという人物は、ドイツ啓蒙主義ないし18世紀史の見直しの中で再評価されてきているわけである。そこで私としてはドイツ啓蒙主義にとって欠かすことのできないこの巨人の多方面にわたる業績を、その生涯の歩みの中で描き出していくことにする。
その前にニコライに対する私の評価について、一言述べておきたい。私の見るところニコライはまずもって、当時ヨーロッパの後進国であったドイツの近代化に向けて、全力を傾けた「文明開化の使徒」であった、という事である。その活動の時期は、18世紀後半のほぼ半世紀に及ぶが、この間古く因習的な宗教支配を打破し、社会の各方面の改革を推進すべく、休む暇なく言論・出版活動を続けた。活動の中心は、ドイツの中では先進的であったプロイセン王国の首都ベルリンであったが、自ら編集にあたった書評誌『ドイツ百科叢書』などを通じて、彼はドイツ全国に「知のネットワーク」を張り巡らしたのであった。その啓蒙活動は、ヨーロッパの当時の先進国であったイギリス、フランス、オランダに追いつくことを目指していた。
ニコライ自身は言論・出版活動を通じて、底辺の民衆教育の推進に力を入れていたが、民衆啓蒙が達成されるには、なおかなりの時間を要した。しかし社会の上層部を形成していた貴族や聖職者の一部は、ニコライなど中流市民や官僚・知識人の啓蒙活動に、身分の違いを越えて参加し、社会の近代化に尽くしたのであった。その結果、ニコライが晩年を迎えた19世紀の初頭のドイツの状況は、彼が活動を始めた18世紀中ごろとは、その様相をすっかり変えていた。
政治面では19世紀初めには領邦国家の数が大きく整理されたが、その体制はなお続き、ドイツの国家的統一は世紀の後半1871年の、ビスマルクによるドイツ帝国の建国にまでずれ込んだ。しかしその前半には、地域的な格差はなお見られたものの、社会の改革は進み、文化は一つの黄金時代を迎えたのであった。いっぽう経済面では1834年のプロイセン主導のドイツ関税同盟の発足によって、ドイツの経済的統一が進み、その後の政治的統一の前提ともなったわけである。また19世紀の前半に鉄道路線の建設が進み、産業革命の推進がみられたのだ。
これらの成果は、ニコライなどの啓蒙主義者たちが、長く続いてきた古い社会体制や宗教支配を打破し、新しい社会や文化が生まれる基盤を営々と築き上げたからこそ、達成できたものと言えよう。その意味でニコライたちの努力は十分報われた、といえるのではなかろうか。
とはいえニコライはそれだけではなくて、それ自体評価されるべき業績も数多く残している。その詳細について、これから順次紹介していくことにしよう。
次回のブログ「ドイツ啓蒙主義の巨人フリードリヒ・ニコライ その2」では、彼の青少年時代を取り上げることにする。
